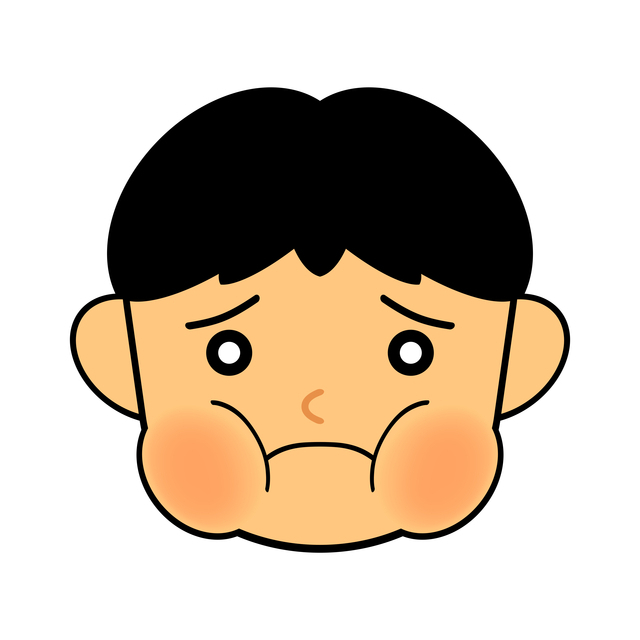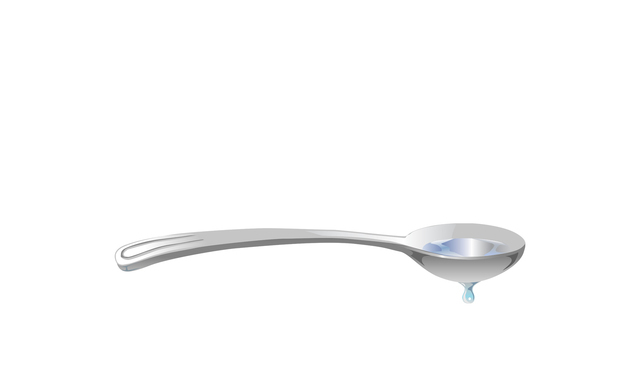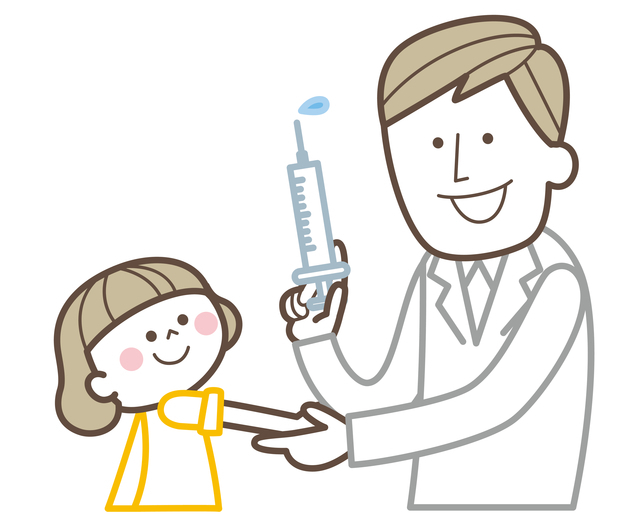おたふく風邪とは
おたふく風邪の免疫とは?
おたふく風邪にかかったことのあるママは、おたふく風邪の免疫をもっています。そのママの母乳にはおたふく風邪の免疫が含まれているため、その母乳を飲んでいる赤ちゃんはおたふく風邪にかかりにくいと言われています。
けれど母乳の免疫効果は生後6ヶ月程度なので、それ以降は母乳を飲んでいる赤ちゃんでもおたふく風邪になる可能性があります。おたふく風邪の予防接種は1歳以降にしかできないため、上の兄弟から移ってしまうことが多いようです。
おたふく風邪の症状
主な症状ー発熱
37度~38度の発熱があります。発熱は3~4日で下がります。約20%の確率で、発熱せずに最初から耳下腺の腫れが出現することがあります。
合併症ー無菌性髄膜炎
ムンプスウイルスが原因で、無菌性髄膜炎を合併することがあります。発熱、頭痛、嘔吐、母乳やミルクを飲まない、元気がなくてぐったりしているなどの症状があります。
約10%の確率で発症しますが、きちんと治療すれば軽症ですむと言われています。乳児は早急な治療が必要になるので、様子がおかしいと思ったら速やかに受診してください。
この記事に関連するリンクはこちら
合併症ー難聴
数万人に一人の割合で、後遺症として難聴になる可能性があります。
合併症ー精巣炎・卵巣炎
思春期以降におたふく風邪にかかると、20~30%の確率で精巣炎、7%の確率で卵巣炎になると言われていますが、乳児がなることはほとんどないようです。
体験談:7ヶ月頃におたふく風邪に
1023.sykさんからの体験談:
発熱する前、いつもより機嫌が悪く頬から首筋らへんが赤いなぁと感じました。その後発熱し、39度前後でした。嘔吐はなく、食欲はあまりなかったです。突発性発疹をまだやっていなかったので、突発性発疹かなと思っていました。
病院は熱が出始めたのでその時行きました。胸の音を聞いて、喉を見てもらい、子どもの頬を触ったりして、おそらくおたふく風邪だねと言われました。
解熱剤の座薬をもらい、血液検査をしたいから、熱が下がってから病院にきてくれと言われました。まだ月齢が低いので、頬もそんなに腫れる事もなく、熱もそんなに高く上がる事もありませんでした。
先生は小さい時にやると知らずにおたふく風邪にかかっていたという事はよくあると言っていました。その後血液検査をし結果はやはりおたふくにかかっていた事が分かりました。
おたふく風邪の原因
潜伏期間
2~3週間の潜伏期間があります。平均すると18日前後です。
ほかの人にうつしやすい期間
発症してから9日頃までは唾液にムンプスウイルスが残っているので、2次感染を起こさないためにも注意が必要です。学校保健安全法の規定では、耳下腺、顎下腺、舌下腺の症状が現われてから5日経過し、全身症状がよければ登園可能となっていいます。
この記事に関連するリンクはこちら
ホームケア
患部を冷やす
耳下腺の痛みは、冷やしてあげると軽減します。保冷剤をタオルなどでくるんで、腫れている部分にあててあげましょう。冷やし過ぎると皮膚にダメージを与えてしまうので、保冷剤を直接皮膚にあてるのはやめてください。市販の冷却ジェルシートを貼るのもおすすめです。
予防接種
予防接種を受けるメリット
予防接種を2回接種することで、約90%の人が免疫を得ることができます。一人一人が予防接種をすることで、おたふく風邪の流行を防ぐことができるでしょう。おたふく風邪自体は軽症ですむ病気ですが、合併症がおこる場合もあるので、予防接種をすることをおすすめします。
予防接種の副作用には、微熱、軽い耳下腺の腫れ、約1000~2000人に一人の割合で無菌性髄膜炎の発症があるといわれています。
専門機関へのご相談はこちら
※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。
厚生労働省・子ども医療電話相談事業
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
まとめ
おたふく風邪について解説させていただきました。予防接種についてはいろんな考え方がありますが、子どものうちに免疫をつけておくと安心できますよね。おたふく風邪になってしまったら、合併症と脱水に注意してください。感染力が強いので、2次感染の予防も忘れないようにしましょう。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。