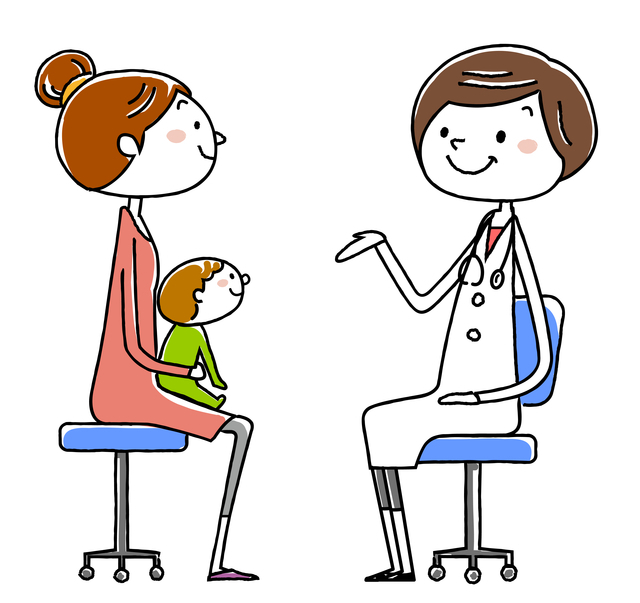目次
産後6ヶ月はこんな時期
離乳食について

この時期になると、離乳食をスタートしている、あるいは始めようとしているという赤ちゃんも多いかと思います。まだご飯から栄養を摂れるほどの量や種類は食べられない頃なので、栄養はミルクやおっぱいから摂るというのが基本です。
あくまで目安の授乳量としては、200~220mgを1日に4~5回ほどですが、身体の大きさや食欲には個人差がありますし、離乳食が始まっている場合はもう少し減っていてもおかしくはありません。
ただし、赤ちゃんが太めだからといって自己判断で授乳量を減らしたり、離乳食が始まってすぐ授乳回数を少なくしたりすることは避けたほうが良いでしょう。
まだ夜中にも授乳がある時期ですが、早急に授乳を切り上げたり減らしたりすることは、赤ちゃんを我慢させたり水分不足の状態にしてしまったりする恐れもあります。焦らずゆったりした気持ちで授乳と離乳食の時間を持てると良いですね。
身体と情緒面の発達は?

生後6ヶ月になると、今まではぐらついていたおすわりが安定的になって上手になります。同時に手先の動きも器用になってくるので、おすわりしながら目の前にあるおもちゃを触って遊ぶという事もできるようになります。
ただし、相変わらず何でも口に入れてしまう時期なので、赤ちゃんの周りに危険なものが無いか常にチェックしましょう。
さらに、パパやママなど身近にいる人を家族だと認識しているような行動も見て取れるようになります。
パパやママにはにっこり笑ってくれるのに、知らない人が来ると緊張して顔がこわばったり泣いたりする人見知りが顕著になってくる子もいます。だんだんと社会性を身につけ始めていく時期と言えるでしょう。
産後6ヶ月のママの体調は?
安定してくるが、抜け毛などのトラブルも

一方、産後半年経ったママの身体の変化はどうでしょうか。この頃には、妊娠・出産で消耗した体力もだいぶ回復したと感じる人も多いでしょう。
少しずつ、妊娠前のように行動ができるようになるので、外へ出る機会も増えてきます。普段の買い物やお散歩だけでなく、ちょっと足を伸ばして遠出することも多くなってくるかと思いますが、無理して体調を崩さないように気をつけたいものです。
身体が回復してくると同時に、産後の新たなトラブルや悩みも出てくる時期です。ホルモンバランスの変化により、産後3ヶ月頃から始まる抜け毛も依然として続いているママもいらっしゃるかと思います。洗髪のたびにびっくりしてしまうかもしれませんが、だんだん収まっていく症状なのでご安心を。
体重やお腹のたるみが気になる時期

また、自分の体型や体重も気になり始めます。産後すぐには妊娠前の体型に戻れないことは理解していますし、戻す暇も無いのですが、産後半年も経つとそろそろこのままの体型や体重ではまずいと感じるママが多いようです。
体重は妊娠前に戻ったのに体型はお腹ぽっこりのまま…というパターンもあり、単なる食事制限だけでの体型戻しはなかなかうまくいかないことが分かります。
とはいえ、赤ちゃんの世話をしつつ運動も食事制限もしっかり行うダイエットをするには無理があるものです。赤ちゃんを抱っこしながらスクワットをしたり、背筋を伸ばしてベビーカーを押して歩いたりと、普段の生活に取り入れやすい方法で、気になる身体の部分のエクササイズをするのがおすすめです。
ママの気持ちの変化
体験談
yuixiaさんからの体験談:
初めての出産時は昼間は2人、夜は夫が帰ってきて3人の生活だったので、2人の時は浮き沈みがありました。
子どもがかわいいのはもちろんですが、周りが仕事をしたりしてると自分だけ社会から置いてかれるという不安があったりして落ち込んだり。泣くたびにおむつのチェックやお腹が空いたのかな?とか毎日、同じ事の繰り返しで疲れたりもしました。
でも、小さくてかわいい時期はほんの少しの時期。今思えば専業主婦で毎日、家にいて子どもの成長が毎日見られて幸せな時期だったと思います。夫が帰ってきた時は何かホッとして肩の荷がおりたような、それだけ気が張ってたのかなと思います。
2人目の時は上の子がいたので毎日賑やかで、上の子が、うるさいほど明るい子なので、私の気も紛れ考える暇がないほどでした。
ぺぃさんぴさんからの体験談:
6ヶ月になり、おすわりができるようになったと同時に、ずっとできなくて不安に思っていた寝返りもできるようになったので安心しました。初めての子で、少し遅いとすぐ不安になってしまいました。
離乳食も始めて、失敗してはいけない、ととても神経質になってしまいました。保健師さんに相談をして、具体的な具材や作り方まで聞いてやっと安心して始めることができました。あとは、少し鼻水が出ただけで不安になっては、実家の母や夫に相談をしていました。
疲れを感じやすい産後6ヶ月の過ごし方
夫婦の時間を大事に

産後6ヶ月の月日が経ったとは言っても、育児はまだ始まったばかり。初めての赤ちゃんの世話に奮闘して、知らぬ間に疲れやストレスが溜まってしまうママも多いはず。
ストレスや悩みを一人で抱え込まないためにも、一番身近にいるパパに話を聞いてもらったり、ママ一人の時間を作ってもらったりすることが重要です。産後は、忙しさや疲れなどからパパとの時間が取れなくなりがちです。
自身の身体や赤ちゃんが心配で、セックスに恐怖心を覚えたり、育児真っ最中のママモードであるが故にまだその気になれないなど、パパとの夜のコミュニケーションがうまく取れないこともあります。
そのような場合、無理にパパの気持ちに応えて我慢することは避け、「今はまだ体調や赤ちゃんが気がかりなので、もう少し待って欲しい」などと、正直に今の自分の状態や気持ちを伝えられると良いのではないでしょうか。
この時期に無理にセックスをすることは、その後の夫婦生活に良い影響を及ぼすとは言えないので、スキンシップやマッサージなどの異なる方法でパパとのリラックスタイムを持つのがおすすめです。
2人ともゆったりとした気持ちであれば、育児に関する悩みや不安も共有しやすいかもしれません。育児中は休む暇も無いと感じるかもしれませんが、夫婦間のコミュニケーションをほんの少しでも意識してみることで、パパとママとの良い協力体制が取れていくことでしょう。
パパにイライラする時は?
育児、家事、仕事復帰…ママはいっぱいいっぱい

育児に必死になってきた産後の月日をふと振り返る余裕も生まれる頃かもしれません。そんな時、まるで自分一人だけが頑張ってきたように、我慢してきたように感じることはないでしょうか。
そのように感じてしまうママは、もしかしたらパパの育児に対する姿勢に不満を持っているのかもしれません。育児は本来、パパとママの両方が協力し分担して取り組むものです。
しかし、パパとしての意識がママの意識より芽生えるのが遅かったり、パパの仕事が忙しかったり、さまざまな理由によりパパの育児参加率の低さが社会的な問題にもなっています。
パパが育児に積極的でない状態が続けば、ママのストレスになることはたやすく想像がつきます。ママは育児だけでなく家事に関しても、パパよりたくさんの役割を担っていることが多いからです。さらに職場復帰もしなければならないママの場合は、時間の制約も大いに出てくることでしょう。
パパに対して不満が募っていくまでママが我慢してしまうと、ちょっとした拍子に気持ちが爆発して、つい攻撃的な物言いになったり、常にパパに対して不機嫌になったり、大きな夫婦喧嘩につながってしまうことも考えられます。
では、どうすればパパに育児に対して積極的になってもらえるのでしょうか。
育児の悩みや喜びを共有する!

まずは、育児の悩みや子どもの成長の喜びをパパと共有することを忘れないでください。
パパが仕事から帰ってきたら、「今日はこんなことができるようになったよ」と子どもの成長を話したり、「夜中の授乳が多くて眠いから辛いな」などと、困っている状況に関してもパパに伝えましょう。パパを育児の部外者にしないことが大切です。
筆者は、育児の大変さを実感してもらうため、子どもの写真を撮る時は、笑顔だけでなく、機嫌が悪い顔や泣いている顔も撮って、パパに見せるようにしています。
そうすると、パパも「大変だったんだね」と共感してくれ、「どうしてこんなに泣いたの?」などとこちらの話を聞いてくれるきっかけとなるので、少し気分が楽になるのです。
パパは「お願い」されるのが好き!
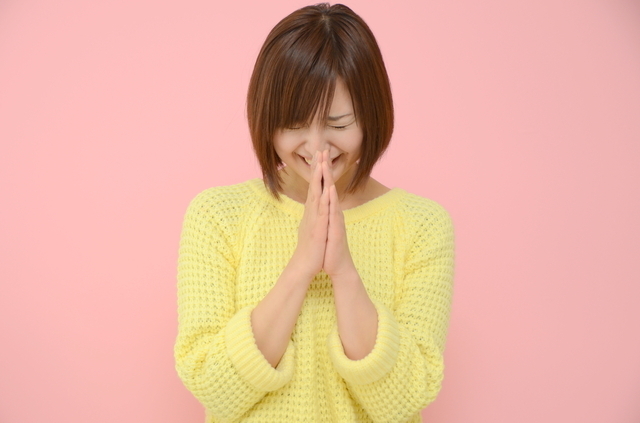
育児に関しても家事に関しても、ママがパパに望む事を具体的な時間や方法を含めた内容で伝える事も効果的のようです。
例えば、「朝起きたらご飯を食べる前におむつを替えて欲しい」だとか、「毎晩脱いだ服は洗濯機の上のかごに入れてね」などといった具合です。
ただ単に「子どもの世話をもう少しやって欲しい」だとか、「自分のことは自分でやって」と言うだけでは、残念ながらパパには伝わり切らないことも多いのです。それどころかパパ自身としてはやっているつもりなのでそれ以上どうしたらいいのかと怒ってしまう場合もありえます。
また、パパは「指示」されるよりも「お願い」されるのが好きで、成果を褒められることでやる気をアップさせる事が多いようです。ママはそれをうまくコントロールするのも手だと言えるでしょう。
産後6ヶ月にパパがやってくれたこと体験談
ママの一人時間をくれたのがうれしかった
E.Tさんからの体験談:
お風呂に一緒に入ってもらえるとうれしかったです。今までは首が安定しなかったので私が入れて裸のまま着替えさせて、とバタバタしてましたが、パパがお風呂にいれてくれると1人でお風呂に入ることができてとてもリラックスできました。
そして、休みの日にパパが2.3時間だけでも預けて、美容院にいったり買い物にいったり自分の時間がもてたときにとてもうれしく感じました。出掛ける際にパパに赤ちゃんを抱っこしてもらったときは重くないし肩が楽で助かりました。
お風呂後のケアをパパと子どものコミュニケーションタイムに
yuzu1215さんからの体験談:
朝早く帰りの遅い、休日もほとんどない仕事をしている主人ですので、家事手伝いはまったくありません。
子どものことは大好きですので、なるべくお風呂は一緒に入れるようにしています。週に1、2回ですが、私が子どもを洗っている間に主人が先にあがり、子どもの湯揚げをしてくれます。それから私はゆっくり自分を洗い流します。
大泣きしていることがほとんどですが、主人と子どもの2人きりの時間も大切ですので、私はゆっくりお風呂に入ります。主人も一生懸命あやし、家の周りを歩いたりして、私があがる頃には泣き止んでいます。
普段は子どもを待たせすぎないように、急いで洗っているので、主人も居るお風呂はかなりうれしかったです。
専門機関へのご相談はこちら
※健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は専門機関へのご相談をおすすめします。以下のような窓口もご活用ください。
助産師会 相談窓口
https://www.midwife.or.jp/general/supportcenter.html
まとめ
産後6ヶ月のママと赤ちゃんについてご紹介いたしました。日々の育児に追われ、出産からあっという間に半年が経ってしまったと感じる人も多いかもしれません。
しかし、まだ半年です。育児はこれから先も長く続くものですから、焦らず無理をしすぎず、ママは自分の身体と心を気遣って過ごせると良いですね。
(文章作成:caltoids)
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。