目次
産後8ヶ月はこんな時期|赤ちゃんのできることが増えます
赤ちゃんの身長・体重は?
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com体重よりも身長の伸びが大きくなります。また、動きも活発になってきますので、すこしすらりとしてきます。
身長、体重の平均は、男の子だと66.3~75.0cmで7.0~10.1kg、女の子だと64.4~73.2cm、6.5~9.6kgです。ただし、赤ちゃんによって体型に特徴が出てくる時期ですので、平均値から外れていても心配ありません。
授乳回数はどれくらい?
母乳、ミルクとも、授乳間隔は4時間程度になってきます。離乳食をあげた後に補うように授乳しましょう。ミルクでしたら、1回あたり200~220mlが目安です。
離乳食はどんなものをあげればいいの?
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com舌や歯茎でつぶして食べることができるようになります。おかゆは少し粒が残る5倍~7倍粥にし、その他の食材も徐々に大きくしてみましょう。
また、自分で食べたがりますので赤ちゃんにエプロンをつけたり、下に新聞紙やレジャーシートを敷いたりして、汚れてもいい環境をつくってあげましょう。手づかみで食べられるものを用意してあげると喜びます。
離乳食は1日2回とし、1回あたりの量は以下が目安です。
・おかゆ 80g
・野菜や果物 20~30g
・魚 10~15g/肉10~15g/豆腐 30~40g/卵 (卵黄なら1個、全卵なら1/3個)/乳製品 50~70g
肉や魚といった、たんぱく質も食べられるようになります。どれか1品、例えば魚だったら10~15g、乳製品なら50~70gをあげましょう。
新しく挑戦する食材は1日1つまでにしておくと、アレルギーがでた場合に原因となった食材を特定しやすいです。
また、卵、特に卵白はアレルギーを起こしやすい食材ですので注意が必要です。固ゆでにして、はじめは卵黄だけあげるようにしましょう。
卵白は、卵黄をあげはじめて1~2ヶ月経ったころからあげはじめると良いです。その場合も固ゆでにしてください。離乳食は時間のあるときにまとめて作っておいて、製氷皿などに小分けにして冷凍しておくと便利です。
健診ではなにをするの?
自治体によって異なりますが、一般には6~7ヶ月検診や9~10ヶ月検診を受ける時期です。6~7ヶ月検診では、寝返りやおすわりなどをポイントに体の発達状況などをみていきす。
また、9~10ヶ月検診では、ハイハイやつかまり立ちなどをポイントに体の発達状況をみるほか、積み木を使ったテストなどで精神面の発達状況などもみていきます。
歯が生え始めたら歯磨きをしましょう
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com歯が生えはじめますので、歯ブラシを使っての歯みがきをはじめましょう。赤ちゃんの歯は柔らかいですので、優しくみがいてあげてください。
また、上唇と歯茎をつなぐ筋(上の前歯の上にあります)に歯ブラシがあたると痛がりますので、指でそっと押さえて保護しながらみがきましょう。
本能的に口をさわられるのを嫌がりますので、楽しい雰囲気づくりが大事です。歌をうたったり、パパやママ、好きなキャラクターと一緒にみがいたりしてみると良いですね。
ハイハイやつかまり立ちができるように
腰が据わり上手におすわりができるようになります。また、腹ばいで前に進むずり這いから、ひざを使って進むハイハイへと変化していきます。早ければつかまり立ちをすることも。赤ちゃんは頭が重い上に上手に動けませんので、転んで怪我をしないよう気をつけてあげてください。
ハイハイやつかまり立ちは目に見える変化ですので、つい他の赤ちゃんと比べてしまい、うちの子はまだ…と思ってしまいがちです。でも、赤ちゃんはちゃんと自分のペースで成長していますので、ゆっくりと見守ってあげましょうね。
後追いがはじまります
個人差はありますが、早いと後追いをしはじめます。ママの姿がみえなくなると泣きながらママを探してついていこうとしますので、トイレや家事ができず困ってしまうことがあります。
また、ママを探して思わぬところへ行ってしまい怪我をする危険も。ベビーゲートやベビーサークルを使って台所や階段、お風呂場など危険な場所には入れないようにしておきましょう。
また、余裕がある時は後追いさせて、ママが何をしているか見せてみましょう。そして、赤ちゃんの前から離れるときは一声かけてみましょう。ママは離れてもまた戻ってくるから大丈夫、と認識していけば後追いは徐々に減ってきます。
ママの体調|頭痛などの体調不良は骨盤矯正で改善も
抱っこやおんぶが増え、頭痛や肩こりに
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com夜泣きや後追いのために抱っこやおんぶをする時間が増え、ひどい肩こりになる方も多いです。肩こりもひどくなると頭痛や吐き気を感じるようになります。
ゆっくりお風呂につかったり、マッサージをうけたりしましょう。ジョギングやストレッチなど体を動かしてみるのもおすすめです。
夜泣きによる睡眠不足
夜中に泣きだし授乳や抱っこをしても泣きやまない…そんな夜泣きがピークとなる頃でもあります。夜泣きの原因ははっきりとはわかっていないのですが、赤ちゃんの睡眠サイクルを整えてあげることで徐々に減っていくといわれています。
朝は決まった時間に起こして日光を浴びさせ、夜は寝る前から部屋を暗くして気分を落ち着かせましょう。夜中に赤ちゃんに起こされる生活がしばらく続きますので、ママは寝不足になりがち。日中、少しでもいいので時間をみつけて睡眠をとりましょう。
生理が再開するママも
約8割のママが産後8ヶ月以内に生理が再開するそうです。妊娠を機にピタッと止まり、1年近く生理のない生活を過ごしてきましたが、また生理と付き合う日々に戻ります。
子宮あたりに痛みを感じたり、原因不明の腰痛があると、もしかしたら生理再開の兆候かもしれません。母乳育児の場合は1年以上生理が来ない場合もあります。焦らなくても大丈夫ですよ。
骨盤矯正で体調を改善しよう
女性にとって大切な骨盤は、出産の影響を大きく受けるため体調にも変化を与えます。産前から骨盤ベルトをしているママも多いかと思いますが、産後も引き続き骨盤矯正をすることが大切です。
赤ちゃんの体重もどんどん大きくなるため、抱っこやおんぶの影響も大きく受けています。骨盤ベルトや整体などで骨盤の歪みを治し、体調を整えましょう。
体験談:生理が再開し、後追いによる抱っこ疲れも
hinano1030さんからの体験談:
産後8ヶ月2週間で腹痛と共に生理が始まりました。二人目の出産が影響しているのかは分かりませんが、一人目の時よりも2ヶ月程始まるのが早かったです。
生後7ヶ月で保育園に預けているため日中のおっぱいのハリがつらいです。なるべく搾乳するようにしていましたが授乳しないので徐々におっぱいの出が悪くなりました。
他には、人見知りや後追いが始まった子どもが、今まで以上に抱っこをせがむようになり腰痛や肩こりに悩まされました。
ママの気持ちの変化|イライラしたら思い切ってリフレッシュ
たまには1人の時間をとることも大切
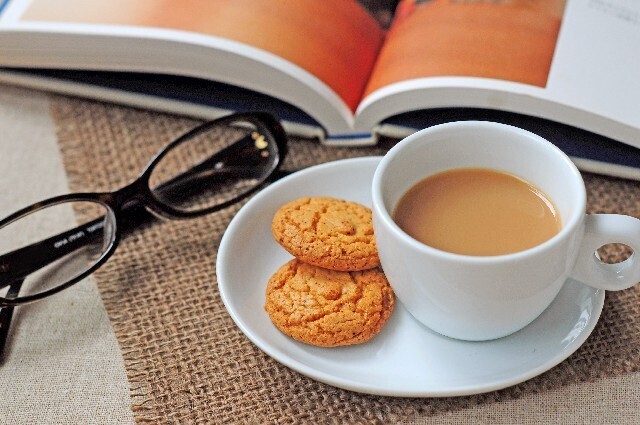 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com赤ちゃんが後追いをする時期は、家事はもちろんトイレに行くことさえ難しくなります。赤ちゃんをかわいく思う反面、イライラしてしまったり、一人になりたいと思ったり…
授乳間隔が4時間ほど空く時期です。赤ちゃんはパートナーやご家族、一時預かり施設などにみてもらい、1人でゆっくり過ごす時間をつくってみてはいかがでしょうか。
イライラし続けていると、ママ本人だけでなく赤ちゃんや家族も辛くなってしまいます。煮詰まってきたなと感じたら思い切って1人になり、リフレッシュするようにしてみてくださいね!
体験談:1人で行動できない不自由さが辛く感じる
maple333さんからの体験談:
身体は割と出産前の状態に戻っているのに、1人で自由に外へ出ることのできないもどかしさを感じるようになってきました。
赤ちゃんのことがかわいくないわけではないのですが、自由に自分の用事を済ますことのできないことに苛立ちさえ感じることもありました。
ずっと外で働いていたせいもあり、家にずっといることへの嫌悪感さえ感じるようになり、なかなか理想と現実とのギャップに慣れるのに時間がかかったように感じました。
産後8ヶ月の過ごし方|赤ちゃんと外の世界で楽しもう
社会的な交流を持ち始めよう
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.comお昼寝の時間も少なくなり、赤ちゃんと向き合う時間が増えてきます。赤ちゃんと一緒に、育児サークルや地域の子育て支援センターなどへおでかけしてみてはいかがでしょうか。
子どもも、他の赤ちゃんにも興味を持ち始める時期です。いろいろなところに連れて行って、たくさんの刺激を与えてあげましょう。
赤ちゃんの腰が据わると、おでかけや外での食事も大分ラクになります。おでかけは赤ちゃんの成長にも繋がりますし、ママ自身もリフレッシュできたり良い効果がたくさんありますよ。
手作りおもちゃを作って親子で楽しもう
暑い日や寒い日、雨の日など外に出られない日はおもちゃを作ってみませんか。空のペットボトルにカラフルなボタンやビーズを入れて、キャップをテープでしっかり止めればガラガラのできあがりです。
レジ袋にマジックで絵を描き、ふくらませて口を止めれば、赤ちゃんが喜ぶ手触りの風船ができます。材料は家にあるものや100均で揃えられることがほとんどで、簡単に作ることができます。
世界で1つのママ手作りのおもちゃは、きっと赤ちゃんも大喜びですよ。ママの気分転換にもなりそうです。
体験談:日中は赤ちゃんが過ごしやすい施設へ
takuairi0303さんからの体験談:
この時期は赤ちゃんがハイハイしだしてかなり危険で神経をたくさんつかったので、なるべく子育て支援施設や児童館にいって他のママさんと交流したり、他の赤ちゃんの様子をみて意見交換したりしました。
赤ちゃんが昼寝したときに家事をすませて、夜は育児につかれて赤ちゃんと一緒に夜9時にはねていました。
朝も規則正しく6時にはおきて洗濯や家事をしていました。赤ちゃんと一緒に散歩にでかけたりしました。赤ちゃんに声をかけて楽しんでいました。
産後8ヶ月の注意点|動き回る赤ちゃんが過ごしやすい空間を
思わぬところに事故の原因が!安全対策はしっかりと
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.comハイハイで家中を移動できるようになりますので、ベビーゲートなどを使って階段やお風呂場、台所などには入れないようにしましょう。
また、なんでも口に入れてしまいますので、飲みこんでしまうおそれのあるものを置きっぱなしにしてはいけません。観葉植物の土なども口にいれてしまうので注意しましょう。
赤ちゃんはどんどん成長していきますので、手の届く範囲は毎日広がります。テーブルや棚の上であっても小物を置かないようにしましょう。
引っ張る力も強いですので、電化製品のコードなどは短くまとめたり、テーブルクロスをはずしたりしておきましょう。
扇風機やストーブはもちろん、赤ちゃんの手は小さいですので、シュレッダーなども危険です。届かないところに置くか、ガードをつけておきましょう。
抱っこでの自転車運転は違法です
外出ができるようになってくると、いろいろなところへ連れて行ってあげたくなりますね。ですが、抱っこでの自転車運転は危険であるだけでなく、法律違反でもあります。絶対にやめましょう。
おんぶでの自転車運転は法律で認められています。8ヶ月頃になると腰も据わっていることが多いので、自転車用のチャイルドシートを利用することが一番安全です。やむを得ず、抱っこ紐をつかって自転車移動する場合はおんぶをして乗るようにしましょう。
アドバイス:赤ちゃんが安全に動き回れるよう対策を
ONOTOさんからの体験談:
ハイハイでどこでも行けるようになり、段差も気にせず進んだり、掴まり立ちを覚えたり、自己主張が激しくなってくる頃です。
目を離すとビックリする事をしているので、なるべく子どもに目を配り、本当に危ないなと思うところ(コンセント、キッチンの包丁等)は、触れないように工夫をするといいと思います。
ハイハイは体力をつける為と思い、なるべく制限しないで行きたい所へ行かせ、掴まり立ちも、倒れた時に手を出せる位置にいたり、クッションマットを敷くと少し安心できると思います。
専門機関へのご相談はこちら
※健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は専門機関へのご相談をおすすめします。以下のような窓口もご活用ください。
助産師会 相談窓口
https://www.midwife.or.jp/general/supportcenter.html
まとめ
産後8ヶ月のママは、生理が再開したり、疲れによる体調の変化が起こりやすいです。家族や公共機関に頼り、リフレッシュする方法を見つけて赤ちゃんとの生活を楽しみましょう。
また、赤ちゃんはどんどん成長しているため、昨日できなかったことが今日はできるようになっているかもしれません。日々、危険なところはないか見直して事故を防ぎましょう。
(文章作成:米奉行)
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。















