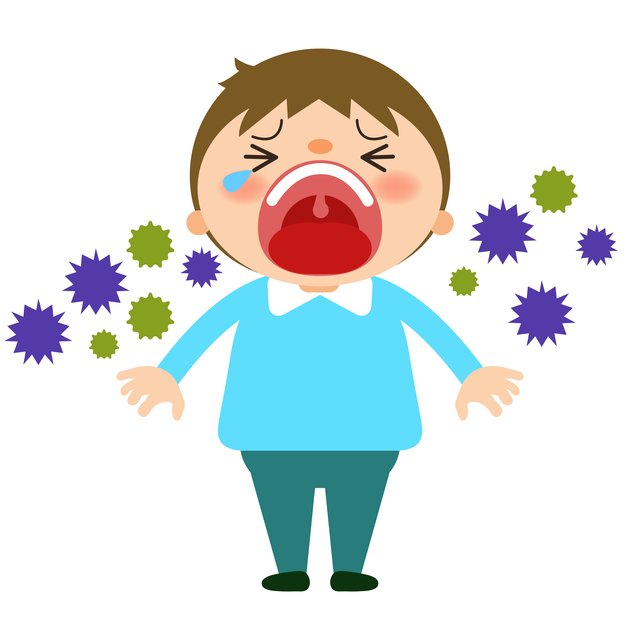RSウイルス感染症について
いつごろ流行るの?
11月~1月に流行することが多いとされていますが、2016年は9月から感染者が増加し、(2012年以降の観測より)9月の患者数は過去最多となっています。今後も感染の拡大が心配されています。
この記事に関連するリンクはこちら
感染しやすい年齢は?
年齢を問わず誰でも感染します。また一度感染しても免疫がつかないため、何度でも感染し生涯感染と発症を繰り返すウイルス感染症です。
名前はあまり知られていませんが非常にポピュラーな病気で、生後1歳までに半数以上の子どもが感染し、2歳までにはほぼ全員が感染すると言われています。
この記事に関連するリンクはこちら
RSウイルス感染症の症状と原因
重症の症状|細気管支炎や肺炎になることも
乳児期早期の赤ちゃんが初感染をすると、重症化しやすいと言われています。乳幼児の初感染のうち約3割が重症化してしまいます。
咳、発熱などの症状が数日続いた後、咳が酷くなり、呼吸するとヒューヒュー、ゼイゼイ言うようになります。呼吸が困難になることから、元気がなくなりぐったりします。細気管支炎や肺炎になることも。
合併症には、無呼吸発作や急性脳症などがあります。これらは命に関わる病気なので、注意が必要です。
感染力
感染力が強いため、集団生活で流行する可能性が上がり、家族間での感染も多いです。
通常感染力が強いとされているのは、発症してから3日~8日程度。しかし乳幼児では、3~4週間も感染力が持続することもあります。
潜伏期間
潜伏期間は2~8日(4日~6日が最多)で発症します。
予防法はあるの?
RSウイルス感染症のワクチンはないため、予防接種で防ぐことはできません。
ただRSウイルスに感染することで命の危険がある、早産児、ダウン症候群、免疫不全、先天性疾患のある乳幼児に限り、感染しないようにする抗体製剤を保険適用で使用することができます。
日常的にできる予防法は、マスクをつけたり手洗いをしっかりしたりして、ウイルスの侵入を防ぐことです。乳幼児がよく触るものを消毒したり、乳幼児に目や鼻をこすらないようにさせることも大切です。
重症化しやすい乳児期早期の赤ちゃんは、RSウイルス感染症が流行している時期には人ごみを控えると良いでしょう。
RSウイルス感染症の検査方法と治療法
治療法
RSウイルス感染症の特効薬はないため、対症療法が中心になりますので、通常の風邪と同じ治療を行います。
発熱している場合には解熱剤を、咳がある場合には去痰剤を、呼吸困難がある場合には気管支拡張剤などを使用します。ステロイド製剤を使用することもあります。
RSウイルス感染症になったら気をつけること
お家でできることは
症状が治まるまでは、自宅でゆっくりと過ごすようにしましょう。空気が乾燥していると咳が酷くなるので、加湿器などで調整してください。
発熱していたり元気がなかったりする時には、無理に入浴させる必要はありません。汗や汚れが気になる場合には、絞ったタオルで拭くようにしましょう。
ミルクや母乳は通常通りで飲ませてください。離乳食や食事は、いつもよりも消化が良い食べやすいものがいいでしょう。食事が食べられない時でも、脱水を防ぐために水分補給だけはしてください。
子どもの様子をしっかりと観察し、水分がとれない、呼吸困難がある、元気がなくぐったりしているなど、子どもの様子がいつもの風邪と違うと感じた場合には、速やかに小児科を受診するようにしてください。
専門機関へのご相談はこちら
※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。
厚生労働省・子ども医療電話相談事業
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
まとめ
RSウイルス感染症についてご紹介させていただきました。流行ってきているので、マスク着用、手洗いなどの予防をしっかりとして感染を防いでくださいね。
感染してしまった場合には、周りにうつさないようにする配慮も忘れないようにしましょう。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。