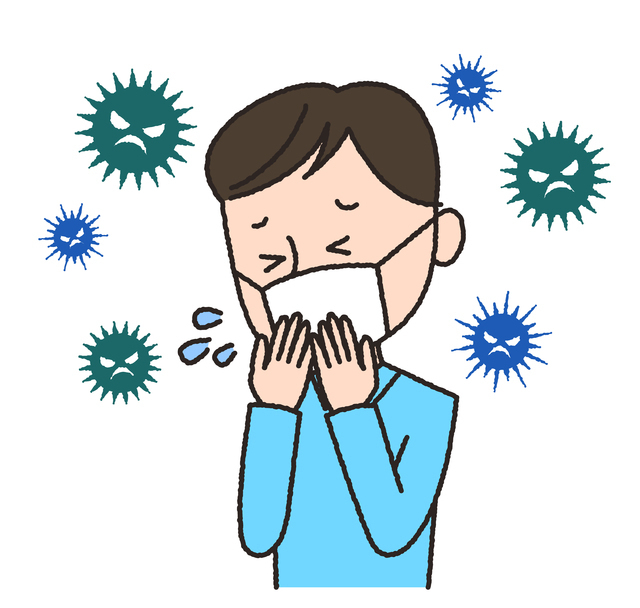麻疹(はしか)とは
感染力
麻疹の感染のしかたは
・接触感染(ウイルスがついたおもちゃや手すりなどを触ることでうつる)
・飛沫感染(咳やくしゃみでツバや鼻水を介してうつる)
・空気感染
があります。
飛沫感染と空気感染のちがいって何でしょう?飛沫感染はゴホゴホやハクション!で飛んでくる水っぽいもの。ある程度距離があれば届きません。
しかし空気感染は、そのゴホゴホやハクションで飛ばされたツバや鼻水が乾いて、軽くなったウイルスがフワフワと空気中に漂ってうつっていくことなんです。
軽いので、長い間空気中に浮いて、遠くまで飛んでいきます。そして、小さいので吸いこんだら体の奥まではいってしまうというやっかいなものです。
つまり、体育館や同じ施設内に麻疹に感染している人がいたら、直接の接触がなくても感染する可能性があるくらい、非常に感染力が強いというわけです。
しかも感染したら100%に近い確率で発症するといわれています。他人への感染力は症状がでる1日前~発疹が出てから4~5日目くらいだといわれています。マスクでの予防は難しく、予防接種が唯一の予防法となります。
何度も感染するの?
一度麻疹を発症したら、その免疫は一生続くと言われており、2回目の発症はありません。そのため、発症した人はワクチンを打つ必要はなくなります。
ただし、1歳に満たない時に発症した場合は免疫の維持が十分でない可能性があります。ワクチン接種をする必要があるか、医師と相談したほうがいいでしょう。
子どもの麻疹(はしか)の症状
主な症状

症状の経過によって、カタル期・発疹期・回復期にわけられています。
≪カタル期≫(3~4日間)
●症状
・38℃前後の発熱
・咳、鼻水
・目やに(結膜炎)
・ときに下痢
・コプリック斑(口の中の頬の内側の粘膜にできる白いぶつぶつ)
カタルとは『分泌物の多い症状』のことです。この時期が最も感染力が強いので注意が必要です。麻疹特有の症状はコプリック斑で、麻疹の診断において重要なポイントです。
受診の際、小児科にいくと医師が口の中をライトで照らしてみますよね。あの時、のどの炎症だけではなく、そういうところもチェックしています。
≪発疹期≫(3~4日間)
●症状
・熱がいったん下がってきた、と思ったらまた半日ほどで39℃以上の高熱が出ます。
・顔、首から全身にかけて赤い発疹が出現。数日間かけてひろがり、発疹同士がくっついて赤くもりあがったまだらになります(紅斑)。
この時期が一番辛く、本人も看病する方も大変な時期になります。
≪回復期≫
●症状
・発疹期3~4日がすぎると、しだいに熱が下がり、赤い発疹も色あせて色素沈着(黒ずみ)へと変わっていきます。
このとき合併症を起こしていなければ10日ほどで治っていきます。回復していく期間ですが、免疫力が低下しているため他の感染症にかかると重症化しやすいので注意が必要です。また、体力が回復するまでには1ヶ月ほどかかることもあります。
発症期間
カタル期:3~4日
発疹期:3~4日
回復期:発疹が出てから3~4日目以降の症状が落ち着いてくるころ。熱が下がってから3日間が過ぎるまでは病日として数え、登校は禁止されています。ざっくりいうと、症状は10日~14日ほどでおさまると考えていいでしょう。
麻疹ウイルスの潜伏期間ですが、麻疹ウイルス感染から10日~12日ほどで発症します。他人への感染力は、症状がでる1日前からだといわれています。
風邪の症状とのちがい
一般的な風邪症状と麻疹の初期症状は似ています。風邪は3~4日で回復にむかいますが、麻疹の場合は日にちがたっても症状が改善せず、発疹や新たな症状が出てきます。
合併症
肺炎、中耳炎、クループ症候群などを合併しやすく、1000人に一人は脳炎を発症するといわれています。脳炎を発症するとマヒや知能障害、命にかかわることもあります。
また、麻疹にかかってから数年後に亜急性硬化性脳炎(SSPE)という難病を発症することがあります。 予後不良で現在治療法は確率されていません。SSPEは1歳未満や免疫力が低下しているときに麻疹にかかった場合に多く発症するといわれています。
クループ症候群は、のどの炎症で腫れを起こし、気道がせまくなります。呼吸が苦しそう、変な音がする、咳の音がおかしい、などの時は窒息の危険があります。人工呼吸や気管切開などの処置が必要となる場合があるのですぐにかかりつけ医に相談しましょう。
今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら
麻疹の原因
麻疹ウイルスが原因
麻疹ウイルスは、感染した人が使ったものに付着・飛沫に混じって、体外に放出されてから2時間ほど感染力を保って活性しつづけます。
感染力の非常に強いウイルスで、麻疹の免疫のない人の集団に感染者が一人いたら、12~14人の人が感染すると言われています。インフルエンザは同条件で1~2人ということからも感染力の強さがうかがえますね。
子どもの麻疹の治療法
治療方法
ウイルスに効く薬は今のところありません。対症療法といって、出ている症状に対する薬をつかって苦痛な症状をやわらげるという治療がメインとなります。熱に対して解熱剤(アセトアミノフェン)、咳に対して鎮咳薬、といった感じになります。
細菌の二次感染を防ぐ目的で、抗生剤を投与することもあります。またガンマグロブリンという血液製剤の注射で、発症または重症化をふせぐことができるともいわれています。
ただし血液製剤もまったくリスクがないものではないので、メリットデメリットをふまえた慎重な判断のもと使用されています。
出席停止
麻疹とわかったら幼稚園、保育園、学校にすぐに連絡し、休まなければいけません。休む期間は熱が下がってから3日がすぎるまでになります。
学校保健安全法という法律で決められており、学校を休んでも欠席扱いにはなりません。しばらく休んでから「実は麻疹だったんですよ~」ではだめなんです。他の人に感染を広げないために、すぐに連絡しましょう。
この記事に関連するリンクはこちら
麻疹の予防接種
予防接種のタイミング

麻疹の予防接種は
・1歳になってから
・小学校に入学前の一年間
の2回となっています。
1歳が過ぎてからというのは、生後6ヵ月未満はお母さんからもらった抗体があるためにウイルスに感染しにくいのですが、10ヵ月ごろからその抗体も減っていくためにかかりやすくなるためです。
1歳をすぎてから予防接種をすることで十分な免疫ができます。1歳を過ぎたら早めに予防接種をすることをおすすめします。そして、2回目を打つことでほぼ確実に感染を予防することができます。
もし抗体を持たない人が麻疹を発症した人に接触してしまった場合は、72時間以内ならワクチンの効果があるといわれています。ただし、そのワクチン接種は生後6ヶ月を過ぎている人が対象です。
この記事に関連するリンクはこちら
予防接種したのに
一度予防接種していても時間と共に免疫力が低下し、大人になって感染してしまうことがあります。接種歴や罹患歴(かかったことがあるかどうか)がわからない場合は、医療機関で採血検査することにより調べられます。
ホームケアのポイント
脱水症状に気をつける
高熱と口内炎の痛みにより脱水をおこしやすくなります。まめな水分補給を心がけ、おもうように水分がとれずぐったりするようなときは、医療機関に相談して点滴をしてもらうと楽になります。
小さいお子さんの場合は、スポーツドリンクを製氷皿で凍らせてから小さくし、少しずつ口に入れてあげると水分をとりやすいですよ。
脱水がすすむとさらに熱があがる悪循環になります。口の中が乾いていたり、おしっこが少ないときは脱水のサインです。気を付けて様子を見ましょう。
病後もしばらく休養が必要
麻疹は熱が下がってから3日ほどは他の人へ感染してしまう可能性があると言われています。また、病気によって体力を消耗し、免疫力も下がっているので他の病気にかかりやすい状態にあります。熱が下がっても油断せず、しっかり体をやすめましょう。
専門機関へのご相談はこちら
※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。
厚生労働省・子ども医療電話相談事業
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
まとめ
子どもの麻疹について、詳しくご説明してまいりました。かわいい我が子をこんな辛い病気にはしたくない!そう思いますよね。麻疹に限らず口の中に赤みや腫れ、ブツブツがでる病気は他にもあります。
その異常にいち早く気付けるように、歯みがきの時など意識して口の中を見てみてください。元気な時の状態を知っていれば、異常に早く気づけます。
麻疹は、予防接種さえしていれば防げる病気です、お子さんのを済ませてほっとしているパパママ、ぜひご自分の予防接種歴や罹患歴もふりかえってみてくださいね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。