意外と知らない出産予定日計算法
最後の生理開始日から?推定排卵日から?
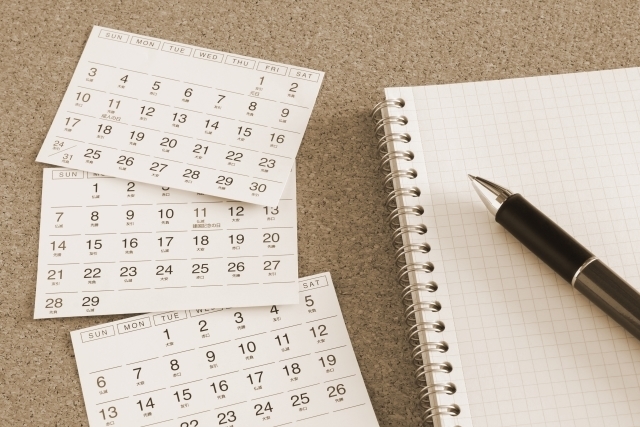 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com日本の産婦人科では、出産予定日を「最後の生理が始まった日から数えて40週0日目(280日目)」(基礎体温からの情報や人工授精日・採卵日などから推定排卵日が判明している場合には「推定排卵日+266日目」)としています。
一般的には、以下のネーゲル計算法という方法で出産予定日を算出します。
A:出産予定の月=最後の生理が始まった月-3(3が引けない場合には、9を足す。)
B:出産予定の日=最後の生理が始まった日+7(その月の日数をこえたら、翌月に繰り越す)
と計算し、「A月B日」が出産予定日となります。
例えば、最後の生理が12月30日であれば、Aは9、Bは37となります。Bは9月の日数をこえていますので、翌月に繰り越し、出産予定日は10月7日となります。
出産予定日に出産する方は少なく、15~20人に1人といわれています。あくまでも大まかな目安だと考えておくと良いようですね。
補正する必要があることも
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.comこの出産予定日は、生理の周期が28日の方を基準にして算出しています。そのため、生理の間隔が長かったり、生理不順であったりする方だと、出産予定日が違ってきます。
その場合、超音波検診(エコー)で赤ちゃんの様子を見て、
・妊娠11週頃までは頭からおしりの長さ(頭臀長)
・妊娠12週以降であれば頭の耳から耳までの長さ(児頭大横径)
を測り、妊娠週数を推定して予定日を補正することもあります。ですが、ズレが一週間以内であれば補正しないことも多いんだそう。予定日に出産する方ばかりではないというのも頷けますね。
予定日を過ぎたら?
正期産であれば大丈夫
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com出産予定日を1日、2日と過ぎると不安になってくる方は多いですよね。しかし、前述の通り、出産予定日通りに出産している方は15~20人に1人いるかいないか程度だといわれています。
出産に一番適している期間は出産予定日の3週間前(妊娠37週0日)から2週間後(妊娠41週6日)の間です。この期間に出産することを正期産といい、ほとんどの方が正期産となります。
なお、傾向としては初産の方は予定日よりも遅くなることが多く、経産婦さんは予定日よりも早まることが多いようです。
予定日をすぎると、周囲からのまだかしら、という視線が気になってしまうかもしれません。ですが、ストレスを感じてしまっては良くありません。
出産予定日は、あくまでも目安です。赤ちゃんが元気であれば、予定日にはこだわらなくても大丈夫ですよ。
遅れた場合の検診内容
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com予定日を過ぎると、いつ産まれても良い状態ですので、妊婦検診がこまめに行われるようになります。検診ではエコーなどで赤ちゃんが元気に育っているか、胎盤の機能が落ちていないか、羊水は十分な量かどうか、などを検査します。
一般的に妊娠42週未満であれば胎盤は正常に機能していますので、予定日を過ぎても問題はありません。お母さん・赤ちゃんともに元気であれば、自然にお産が始まるのを待つことが多いようです。
しかし、赤ちゃんの動きが少ない・脈が速いなど異常がみられた場合は、胎盤の機能が低下している可能性があります。この場合は、陣痛を誘発したり、帝王切開によって出産を行ったりすることもあります。
いつから過期産になるの?
過期産とは妊娠42週以降の出産のこと
妊娠42週以降に出産することを、過期産といいます。この時期になると、胎盤の機能が低下し、胎盤からへその緒を通じて運ばれる酸素や栄養が少なくなります。
そうなると、赤ちゃんが苦しくなって胎便をしてしまうことがあります。胎便で汚れた羊水を赤ちゃんが飲み、肺の機能が低下してしまうことも。
また、赤ちゃんの体重が減ったり、おしっこの量が減ることで羊水が減ってしまうこともあります。羊水が減ってしまうと、陣痛が始まったときにへその緒が圧迫を受ける可能性が高まります。
お産がはじまらないときの医療処置
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com妊娠41週を過ぎてもお産が始まらない場合は、器具やお薬を使って陣痛を誘発する場合があります。
・子宮口を開く
お産が近づくと、ホルモンの影響や、赤ちゃんが降りてくることによって子宮口が開きやすくなります。ですが、子宮口がかたい場合、なかなか開きません。
その場合、膣錠や注射などの子宮頚管熟化剤によって子宮口をやわらかくしたり、器具によって子宮口を広げたりすることがあります。
器具によって処置を行うと、その後1日程度で子宮口が開き、陣痛が始まる方が多いようです。それでもお産が進まない場合は、陣痛誘発剤も使用するようです。
・陣痛誘発剤
飲み薬や点滴などの陣痛誘発剤のみで陣痛を起こす場合もあります。陣痛を起こすプロスタグランディンもしくはオキシトシンによって子宮の収縮を促し、お産を進めていきます。
いつからいつまでが早産?
早産とは妊娠22週以降37週未満のこと
妊娠22週以降37週未満の間の出産を早産といいます。
まだ赤ちゃんの体の機能が整っていないため、NICU(新生児集中治療室)などで適切な処置を受ける場合が多くあります。
早産になる原因は?
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com早産になる原因としては、
・性感染症や破水
・妊娠高血圧症候群
・子宮頸管無力症・頸管短縮例など子宮に異常がある
・糖尿病、歯周病等の持病がある
・前置胎盤、常位胎盤早期剥離
・高齢出産
・喫煙やストレス、疲労
・やせ
などがあるといわれています。また、前回妊娠で早産であった妊婦は、次回以降の妊娠でも早産となるリスクが高いとされています。
また、赤ちゃん側の原因として、
・羊水が多すぎる、または少なすぎる
・双子以上である
などがあると早産につながります。
栄養バランスのとれた食事を摂る、体を冷やさない、適度な運動をする(ですが過度な運動はNGです!)など、生活習慣に気をつけることによって早産のリスクは低下するといわれています。
ただ、残念ながら原因によっては予防できないこともあります。子宮に何らかの異常があったり、赤ちゃんが双子以上である場合は、特に日常生活に注意し、いつもと変わりはないかチェックしておきましょう。
また、妊婦検診で早産になる兆候が見つかることも多いですので、検診は必ず定期的に受けましょう。
早産になりかかっている切迫早産と診断されても、安静にしたり、治療を受けることによって早産を予防することができます。
早産の兆候は?
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.com・下腹部や背部に痛みがある
・お腹が張る
・不正出血がある、おりものに血が混じる
・破水した
こうした症状は、早産の兆候としてあらわれている場合があります。異変があったらすぐに病院へ連絡しましょう。
早産になるとどうなるの?
妊娠週数が早いと、まだ赤ちゃんの体の機能は整っていません。そのため、早産になると、呼吸器系の病気だったり未熟児網膜症、壊死性腸炎、脳室内出血といった病気にかかってしまう可能性があります。
赤ちゃんを元気に育てるため、34週前半未満で産まれた場合は、大きな病院へ搬送され、NICU(新生児集中治療室)に入ることが多いようです。
NICUではどんな処置を行うの?
 出典:www.photo-ac.com
出典:www.photo-ac.comNICUでは、点滴などを使って栄養を補います。母乳が飲めるようでしたら、搾乳した母乳をチューブを使って胃に送ります。
その後赤ちゃんが成長するにしたがって、哺乳瓶を使ったり、また直接母乳をあげたりできるようになります。
また、黄疸や感染症、脳波や眼底検査などの検査も行います。そして体重が2500g超え、赤ちゃんが元気であれば退院できることが多いようです。
心配ではありますが、現在は医療技術の進歩によって元気に育つ赤ちゃんが多いです。退院してきた赤ちゃんを元気に迎えられるよう、お母さんもゆっくり休んでくださいね。
まとめ
出産予定日はあくまでも目安ですですので、予定日を過ぎても心配しすぎる必要はありません。また、早産や過期産であっても、適切な処置を受けることで多くの赤ちゃんは無事に産まれ、元気に育っていきます。
不安なことがあればお医者さんと相談しながら、お産がはじまるのをゆったりと待ちましょう。(文章作成:米奉行)
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。










