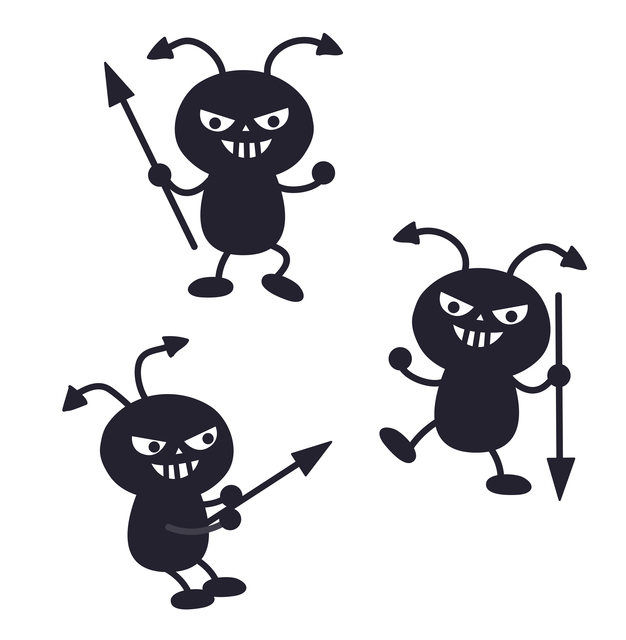目次
ノロウイルス
原因
ノロウイルスの感染が原因です。ノロウイルスは、ノロウイルスに感染した人の便や嘔吐物、十分に加熱されていない、かつウイルスを保有している貝類などに含まれています。
流行る時期
11月~3月の冬に流行ることが多いです。
潜伏期間
約12~48時間の潜伏期間があります。
罹患期間
下痢が治まってから、3日~7日は便の中にノロウイルスが含まれています。
完治の目安
発症から1日~2日が症状のピークです。その後は症状が軽減していき、1週間程で元の状態に戻ります。
治療法&薬
ノロウイルスの特効薬はないため、対症療法(原因に対する治療ではなく、症状を軽減させること)を行います。胃腸症状には整腸剤、嘔吐には吐き気止めの座薬、発熱には解熱剤が処方されることがあります。
この記事に関連するリンクはこちら
ロタウイルス
原因
ロタウイルスによる感染が原因です。ロタウイルスは、感染者の便や嘔吐物に多く含まれています。
流行る時期
冬の間に流行り、3月~5月にも発症します。
潜伏期間
2日~4日の潜伏期間があります。
罹患期間
発症から2週間は、便にロタウイルスが含まれています。
完治の目安
嘔吐は3日前後、下痢は5日前後、全ての症状が治まるまでに、1週間程度かかります。
治療法&薬
ロタウイルスの特効薬はないため、対症療法を行います。胃腸症状には整腸剤を、嘔吐には吐き気止めの座薬、発熱には解熱剤が処方されることがあります。
この記事に関連するリンクはこちら
アデノウイルス
原因
アデノウイルスの40型、41型である、腸管アデノウイルスに感染することが原因です。腸管アデノウイルスは、感染者の便、嘔吐物、唾液などに含まれています。なお、プール熱(咽頭結膜熱)を引き起こすのもアデノウイルスですが、違う型です。
流行る時期
一年を通して発症する病気です。
潜伏期間
3日~10日間の潜伏期間があります。
罹患期間
症状が改善した後にも、体内にアデノウイルスが残ります。のどには7日~14日間、便には30日間含まれます。
完治の目安
下痢が治まるまでに、7日~14日間を必要とすることもあります。
治療法&薬
アデノウイルスには特効薬がないため、対症療法を行います。胃腸症状には整腸剤が処方されることがあります。
子どものウイルス性胃腸炎の症状と治療
腹痛の場合
下痢症状が酷い場合には、腹痛を伴うことがあります。下痢止めが使用できないので、整腸剤で腸の働きを整えます。腹痛がある時には無理して食事をせず、水分補給にとどめましょう。
下痢の場合
便にウイルスが多く含まれているため、体内からウイルスを排除するためにも、基本的に下痢止めは使用しません。排便した後には肛門周囲を清潔にして、脱水にならないように水分補給をしましょう。
頭痛の場合
発熱にともなって、頭痛が起こることがあります。解熱すると頭痛も治まることが多いので、高熱の場合には解熱鎮痛剤が処方されます。また、脱水症状の一つに頭痛があるので、脱水症状になっていないかの注意も必要です。
発熱の場合
高熱がある場合には、解熱剤が処方されることがあります。氷のうや氷枕などで冷やすのも良いですね。
この記事に関連するリンクはこちら
子どものウイルス性胃腸炎で注意したいこと
お風呂
感染している子どもは、最後に入浴するようにしましょう。湯船に入る前には必ず体を洗い、糞便をしっかり洗い流してください。症状が酷く元気がない場合では、シャワーだけでも充分です。タオルなどは家族と共有しないようにし、入浴後にはお風呂をしっかりと清掃してください。
母乳
母乳は消化がいいので、飲めるようなら与えてかまいません。一度にたくさん飲むと嘔吐を引き起こすことがあるので、少しずつ様子を見ながら飲ませるようにしてください。症状によってかかりつけ医の指示が違うこともありますので、医師の指示に従いましょう。
食事(食欲の有無)
【食欲がないとき】
無理して食べなくても大丈夫ですが、脱水症状にならないためにも水分だけは摂るようにしましょう。イオン水、麦茶、白湯などをスプーンで一口ずつ、回数を分けて飲ませるようにしてください。
【食欲があるとき】
吐き気がおさまり食欲がでてきたら、食事を摂ってみましょう。胃腸は弱っているので、消化の良いものを選んでください。うどん、粥、豆腐、バナナなどがおすすめです。脂っこい物や刺激の強いものは避けるようにしてください。
脱水症状
下痢や嘔吐により体の水分が大量に失われることで、脱水症状を起こすことがあります。
・唇が乾燥している
・顔色が悪く皮膚がかさついている
・尿の量が少なく色が濃い
・元気がなくぐったりしている
などの症状がないか、注意して観察してください。これらの症状がある場合には、水分補給をして、速やかに小児科を受診してください。
うつらないようにするには
貝類を食べる時には、しっかりと加熱調理してから食べるようにしましょう。手洗いとうがいを習慣づけて、ウイルスを体内に取り入れないようにしてください。
日ごろから規則正しい生活を送り、体の免疫力を高めることも大切です。感染者の糞便や嘔吐物にはできるだけ近づかず、直接触れない・吸い込まないように心がけましょう。
保育園・幼稚園などの登園・外出
ウイルス性胃腸炎は感染症の一種ですが、いつから登園・外出をしていいかは明確に定められていません。発症から1週間は症状も強く、免疫力・体力が低下しているので、自宅安静がおすすめです。2次感染させないためにも、症状がおさまるまで、できるだけ人と接しないようにしましょう。
症状がおさまったら、医師や園の許可をもらい、登園するといいですね。また、登園許可証が必要な園もありますので、どういった感染症の場合に提出が必要なのか確認しておきましょう。
食中毒との違い
ノロウイルスによる食中毒と感染性胃腸炎は、どちらも「ノロウイルスに感染し、それが原因で、下痢や嘔吐などの症状が出ている」ということを指します。
その具体的な違いは、ウイルスに感染した食べ物を介してノロウイルスに感染し、医師が「食中毒」という診断をすれば食中毒として扱われ、食べ物を介さず接触感染などでノロウイルスに感染した場合は、感染性胃腸炎と言われます。
体験談
yuki0514さんからの体験談:
嘔吐からはじまり、下痢し始めました。食欲はなく、水はかろうじて飲みましたがすぐ吐きました。微熱程度でしたが、嘔吐と下痢のせいでぐったりしていました。
嘔吐が始まってすぐに病院にいきましたが、特にウイルスを特定する検査はありませんでした。下痢を止めてしまうとウイルスが排出されず、症状が悪化してしまうとのことで、吐き気止めのみの処方でした。
まだ生後8ヶ月だった娘は嘔吐と下痢が止まらず、みるみる脱水症状となり、夜中に救急病院を受診し、点滴してもらいました。嘔吐が止まらず、そのまま緊急入院しました。
ウイルス性胃腸炎で一番怖いのがこの脱水症状とのことなので、お子様がまだ赤ちゃんの場合、少しでも様子がおかしければすぐに病院に行かれることをおすすめします。
専門機関へのご相談はこちら
※夜間休日、お子さまの健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は子ども医療電話相談♯8000に相談をおすすめします。
厚生労働省・子ども医療電話相談事業
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
まとめ
子どものウイルス性胃腸炎についてご紹介させていただきました。ウイルス性胃腸炎は、水分補給と安静が大切です。また、感染を広めないように注意してくださいね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。