目次
産後3ヶ月はこんな時期
赤ちゃんの発育と発達

(1)身長と体重の目安
この頃の赤ちゃんは、出生時のほぼ2倍の体重になり、見た目もふっくらとした印象になります。
・男の子 身長 57.5~66.1cm 体重 5.0~8.0kg
・女の子 身長 56.0~64.5cm 体重 4.8~7.5kg
(2)身体発達の目安
個人差はありますが、生後3ヶ月の赤ちゃんはこんなことができるようになります。
・首がすわり始める
・手足の動きが活発になり、動きは左右が一致する
・指しゃぶりしたり、げんこつを口に入れたりする
・手にするものはすべて口に入れる
・軽い物を短時間なら手で持てる
・追視するようになる
・音のする方に顔を向ける
・喃語が出始める
・あやすと笑う
・目の前で両手を合わせることができる
随分と色々なことができるようになります。赤ちゃんのこのような発達を知っておくと、ママパパも赤ちゃんとの遊び方を工夫できますね。
授乳回数と睡眠時間
(1)授乳間隔
この頃になると段々と生活リズムができ始め、1日の授乳回数が決まってきます。母乳の場合は、平均1日6~8回ほど、間隔は3~4時間になります。これまでは、飲みたいだけ飲んでいた赤ちゃんも満腹中枢が働き始めるので、一定量飲めば満足感が得られるようになります。
反対に、いつもおっぱいを欲しがる場合や体重が明らかに増えないといった場合は、多めに飲ませてあげましょう。改善しない場合や心配な場合は、母乳外来などに相談に行きましょう。
授乳回数や授乳間隔は赤ちゃんによって個人差が大きいものですから、平均的ではないからといって心配することはありません。赤ちゃんとママのペースを大切にしてくださいね。
(2)睡眠時間
授乳回数と共に睡眠時間のリズムも整い始める時期です。中には、5~6時間まとまって寝られるようになる赤ちゃんや、夜の授乳からそのまま朝までぐっすりという赤ちゃんも。もちろん、睡眠時間も個人差が大きいので、夜中も2~3時間ごとに起きておっぱいをほしがる赤ちゃんもいます。
まだまだ、夜間の授乳がなくならずに睡眠不足のママもいらっしゃるかと思いますが、赤ちゃんと一緒になって昼寝をするなどして睡眠時間を少しでも確保してくださいね。
生後3ヶ月~4ヶ月健診
3~4ヶ月健診は、自治体により異なりますが、市町村で指定された日に集団で受けることが多いようです。市町村によっては、離乳食の始め方を説明してくれる場合もあります。
【主な健診内容】
〇身長・体重・胸囲・頭囲測定
〇問診
〇栄養状態の確認
〇股関節開排制限の有無
〇首のすわり具合のチェック
〇追視のチェック
ほとんどのママが1ヶ月健診以来のことだと思いますので、緊張と不安半面、赤ちゃんの成長が分かる楽しい時間になることでしょう。問診の時間などを使って、気になる事や心配事は積極的に聞いてみると良いですね。
体験談:赤ちゃんの生活リズム
hinano1030さんからの体験談:
7時に起床して授乳をして、2時間程寝ます。そのあと、9時くらいからグズリ出し、抱っこしてと泣き出します。
少しおっぱいを飲んだあと、遊び飲みを始め、飲まなくなります。そのあと1時間程、おしゃぶりをしたり指しゃぶりをしたり、お話ししたりと遊んでいます。
すると急に火のついたように泣き出し、おっぱいを飲んだあとまた2時間程寝ます。夕方4時ぐらいまでは、そこそこ機嫌よくすごしていますが、そこから2時間位たそがれ泣きで、何をしても泣き続けます。
そのあとお風呂に入り、おっぱいを飲んで9時に就寝。夜中に3度起きて授乳、就寝といった感じでした。
産後3ヶ月のママの体調の変化
尿失禁について
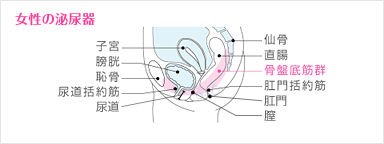 出典:www.kao.co.jp
出典:www.kao.co.jp産後3ヶ月になると、様々な不調を訴えるママが多くなってきます。その一つが尿失禁です。ふいにお腹に力を入れた時やくしゃみした途端にというケースが多いようです。
その原因は、骨盤底筋群の筋肉疲労です。骨盤底筋群とは、子宮、膀胱、直腸といった臓器を下から支えている筋肉群です。この骨盤底筋群が、分娩時のいきみにより疲労し緩んでいます。
そのため産後は、尿道を開け閉めする尿道括約筋の締まりが悪くなり尿失禁が起きてしまうのです。尿取り用のナプキンなどを利用して少しでも不快感をなく過ごしましょう。
この記事に関連するリンクはこちら
骨盤底筋体操のやり方
尿失禁に悩まれているママは、骨盤底筋を鍛える体操を取り入れてみてはいかがでしょうか?これは「骨盤底筋体操」として、マタニティヨガや産後の運動として広く取り組まれている運動です。
ここでは、産後に自宅で簡単にできる方法をご紹介します。
仰向け・椅子に座る・机に手を付くという三つから、家事や育児の場面に合わせたり、自分に合う体勢を選んだりして行うとよいでしょう。
(1)仰向けの場合
脚を肩幅に開き、膝を立てます。体の力を抜きます。肛門と膣の部分に意識を集中させて、肛門と膣周辺をキュッとゆっくり5秒間ほど締めます。
そして、ゆっくりと緩めていきます。この場合は、赤ちゃんのお昼寝の時間など、一緒に寝ながらできますね。
(2)椅子に座る場合
背中を伸ばして姿勢を正し、脚は肩幅に広げます。顔は正面を向きましょう。肩の力は抜き、お腹には力が入らないようにします。
肛門と膣の部分に意識を集中させて、肛門と膣周辺をキュッとゆっくり5秒間ほど締めます。そして、ゆっくりと緩めていきます。こちらは、ティータイムやテレビを観ながらでもできますね。
(3)机に手を付く場合
脚と机についた手は肩幅に開きます。背中を伸ばして、顔は正面に向けましょう。全体重を机についた手にかけます。
肩とお腹の力を抜きます。肛門と膣の部分に意識を集中させて、肛門と膣周辺をキュッとゆっくり5秒間ほど締めます。そして、ゆっくりと緩めていきます。
こちらは、台所で家事をしながらや洗顔・歯磨きのついでにできそうですね。1日に1回でも毎日行うことが大切とされていますので、家事や育児の間に意識して行うだけでもよいかと思います。
骨盤底筋体操は、尿失禁だけでなく産後のスタイルアップや生理痛の改善などにも効果があるとされています。ママにとってはうれしいことだらけですね。
抜け毛について
ママに起こる不調の二つ目は、抜け毛です。産後脱毛症とも言われています。抜け毛の原因は、女性ホルモンの影響、ストレス、疲労、睡眠不足、母乳による栄養不足などが挙げられます。
女性ホルモンの増加により妊娠中に抜けなかった髪の毛が、産後の女性ホルモン減少により、その分抜けやすいとも言われています。
女性にとって髪が抜けるのはとてもショックなことですが、自然に治ることがほとんどです。一時的なものだと思って心配しすぎないことです。なお、半年から一年以上改善しない場合はお医者さんに相談してみましょう。
髪に良いとされるタンパク質やカルシウム、ビタミンやミネラルといった栄養素を取り入れたバランスの摂れた食事を心がけましょう。なかなか思うように栄養素が摂れない場合は、サプリメントを活用するのもおすすめです。
体験談:ホルモンの影響だからと言われて安心
A.Tさんからの体験談:
私は3ヶ月後半に抜け毛が酷くなりました。髪を洗ったり、とかしたりするだけでごっそりと抜け、日に日に髪が薄くなっていきました。家事や育児をするのに長い髪が邪魔で、毎日束ねていたので、さらに抜けやすくなりました。
元々髪の量が多かったので、ボリュームが抑えられてちょうど良くなりましたが、毎日お風呂場の排水口に髪が詰まってしまいました。ホルモンの影響だから気にしなくていいと保健士さんに言われて、安心しましたが、しばらく抜け続けたので、大変でした。
気になる産後の体重戻し
産後3ヶ月、赤ちゃんのお世話が慣れてくると自分にも目がいくようになりますよね。多くのママが産後の体重の戻りや、体型の変化を気にしてしまうのではないでしょうか?
妊娠・出産で体も大きく変化してしまうのは仕方がないとは言え、妊娠前の体重に戻りたいと思いますよね。急激なダイエットは禁物ですが、日々の運動や食事管理で徐々に戻せていけると良いでしょう。
この記事に関連するリンクはこちら
産後3ヶ月のママの気持ちの変化 ”産後うつ”とは?
適切な治療を受ければ回復します!

産後3ヶ月になると、体調面だけでなく精神面にも不調が出てくることがあります。特に注意したい心の病気が「産後うつ」です。
産後うつとは、抑うつ状態や物事に対する興味や楽しみを感じなくなるといった症状が、産後2週間以上続く病気です。産後のマタニティブルーとは区別されています。
以下は、日本産婦人科学会の「産後うつ病の症状」を参考にまとめたものです。
【主な症状】
1.抑うつ気分、不安、焦り、不眠
2.母親としての責務を果たせないことに対して、自分を責めてしまう
3.子どもや夫に対して愛情が涌いてこないことで自分を責めてしまう
4.育児に対する不安や恐怖心がある
5.重症化すると自殺を考えるようになる
このような症状が出ている場合は、産後うつを発症している場合があります。ママ本人が気づかないケースが多いので、身近にいるパパや家族が気にかけてみる必要があります。
自治体によっては、保健師や助産師による家庭訪問の際に、産後うつチェックのためのアンケートを実施しているところもあります。
産後うつは、適切な治療を受ければ回復する病気です。少しでも異変を感じたら早期に医療機関を受診することが大切になります。
この記事に関連するリンクはこちら
体験談:産まれた時よりも愛しい
くっきーまるすけさんからの体験談:
生後間もない頃は赤ちゃんがふにゃふにゃでこわごわ抱っこしていましたが、3ヶ月を過ぎるとだいぶ首がしっかりしてきて、縦に抱っこする事も出来るようになりました。
笑顔も増え、かわいいと思うことが多くなりました。産後すぐは周りに対しても少しピリピリしていたようですが、気持ちが落ち着き、赤ちゃんに対してもゆとりを持って接せられていたように思います。
自分を目で追ってくれているようで、産まれたての時よりもさらに愛しく感じるように思いました。
産後3ヶ月の過ごし方
ストレスを感じるのは当たり前
産後3ヶ月のママのほとんどが、落ち込んだりストレスを感じたりする経験があることと思います。この産後のストレスには、ホルモンバランスの乱れも大きく関係しています。
産後は、エストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが減少し、反対にプロラクチンという母乳を作り出す女性ホルモンが増加します。
このような急激なホルモンバランスの変化により、精神的なストレスを感じやすくなっているのです。いわばストレスを感じて当たり前の状態にあるのです。
ですから、ストレスを感じてしまう自分を責める必要はありません。ママひとりで、育児も家事も完璧にやらなければいけないという考えをやめて、可能なことからパパに赤ちゃんのお世話を頼んでみてもいいでしょう。
短時間でも育児ストレスから開放され、ママひとりの時間を作るのもよいですね。パパや家族に赤ちゃんを預けて、カフェでお茶をしたりゆっくりお風呂に入るだけでも随分と気持ちが軽くなります。
また、赤ちゃんのお散歩も兼ねて、地域の児童館や子育て支援センターなどに出向いて、他のママとおしゃべりするのも気分転換になりますよ。
その他にも、絵本の読み聞かせやベビーマッサージ講習などに参加してみるのもいいですね。自治体では様々な子育て支援を行っていますので、ぜひ活用してみてください。
体験談:ママの体調管理をしっかりと
poohkuniboさんからの体験談:
とにかく睡眠不足なので、眠れる時、体を休めるタイミングできたら、絶対に少しでも横になることです。産後は不規則な生活になってしまうので、とにかく自分のこともケアすること。
かわいい我が子をずっと見ていたいかもしれないけど、その我が子を守るのは母である自分なんだから、体調管理をしっかりとすることです。
気持ちを落ち着かせる為に、紅茶とかハーブティーを飲んだり、好きな音楽を小さい音で聴いたりとか、とにかく好きなことを少しずつ取り入れて、育児を楽しみながら行うことです。
体験談:赤ちゃんと積極的に外出を
hinano1030さんからの体験談:
この時期は、赤ちゃんと一緒に外に散歩に出かけたり、一緒に買い物に行ったりと積極的に外出をしていました。家の中だけだと、赤ちゃんと私の二人きりなので、気が滅入るのを防ぐためでもありました。
また家族にもたくさん会い、悩み事があるとすぐ相談するようにしていました。ある日には、赤ちゃんとお昼寝したりとゆっくり過ごしたりもしました。なるべく家事などは、旦那に手伝ってもらい3人でゆっくり遊べる時間を作るようにしていました。
産後3ヶ月の注意点 ”産後クライシス”
産後クライシスとは

「産後クライシス」とは、「産後は夫婦の愛情にとって危機」という現象をNHKが番組で取り上げ、名付けられた造語です。最近よく聞かれる言葉ですね。主に、ママからパパへの愛情が低下する状態です。
愛情が低下する原因は、主に次のようなことが挙げられます。
・産後のホルモンバランスの乱れ
・子ども中心の生活で自分の時間が取れない
・育児参加が十分でないパパへのいら立ち
・子育ての大変さがパパに理解してもらえない
・夫婦間でのコミュニケーション不足
・思いやりやねぎらいの言葉不足
こういったことが原因で離婚につながるケースが年々増加しており、離婚ケースの3割が、子どもが0~1歳のうちになされているという統計があります。
離婚には特別なケースももちろんあります。しかし、愛し合って結婚して大切な赤ちゃんを授かった夫婦が、愛情の低下が原因で離婚というのは悲しいことですね。
では、どのように防いでいけばよいのでしょうか。まずは、このような危機が起こりうるという意識を持つことが大切かもしれません。その上で、相手にしてもらいたいことはできる限り言葉にして伝えたり、常に感謝の気持ちを表したりする、という意識的な行動が必要ですね。
とはいえ、お互い余裕のない時はありますし、喧嘩してしまうのは仕方ないことです。そんな時の体験談として、物理的な距離を置いて仲直りの方法を考えたという話も・・。ママは息抜きを兼ねて実家に帰ることで冷静になる場所を作り、パパは仕事の合間に一言メールで謝ったとのことでした。
いつも夫婦円満というのは子育て中は難しいものですが、大切な赤ちゃんのためにも夫婦間の愛情を保っていきたいものですね。cozreでも産後クライシスに関して記事をまとめておりますので、参考にしてくださいね。
この記事に関連するリンクはこちら
体験談:どうして自分だけ?とイライラが募る日々
マメガシさんからの体験談:
子どもが生後6か月になるぐらいまでは、主人が仕事から定時で帰れることが多く、お風呂に入れてもらっていました。夜の寝かしつけや夜中のミルク作りなども一緒にやってくれて、主人に対し大きな不満はありませんでした。
しかし、生後7か月あたりから、主人の仕事が激務になり、毎日残業が続いたり、土日の出勤も増え、子育てに対する私一人の負担がかなり大きくなりました。
手のかかる男の子だったため、毎日身も心もすり減っていきました。疲れ切った体で、主人の夕飯を作ったり、主人の洗濯物を洗ったりすることが苦痛になっていきました。
育児だけでも大変なのに、どうしてあなたのために体と時間を使わなきゃいけないの?二人の子どもなのに、どうして私だけがこんなに大変な思いをしなくてはいけないの?と主人に対し、怒りや憎悪の感情が芽生え、自分でも抑えきれなくなりました。
体験談:気持ちや環境を切り替えて、夫に育児の方法を教える
まゆしずくさんからの体験談:
一緒にいるのが辛くなって、あまり赤ちゃんを長距離の移動はさせたくはなかったのですが、出血の事もありましたので、3ヶ月ほど実家に帰り、両親の助けを借りました。
心が落ち着いてから、主人に週末来てもらって、赤ちゃんのお世話を教えました。授乳だけは、私しかできなかったので、おむつ替えとお風呂に入れるのは、徹底的に指導しました。
夜中の授乳も、病院に聞いて、体が辛ければミルクを与えてもいいという事だったので、主人が泊まってる時に、ミルクの調合も教えて、ミルクの授乳も教えました。
そして、出血を収まった頃に、自宅に戻りましたが、実家での徹底的指導してが良かったのか、わたしが体調不良の時は、自分からおむつ替えやお風呂タイムやらをやってくれましたし、家事もきちんとできるようになっていました。
その後も、夜泣き対策も主人からやってくれたので、産後クライシスは改善されました。
専門機関へのご相談はこちら
※健康状態に心配なことがある場合や受診の目安に迷った場合は専門機関へのご相談をおすすめします。以下のような窓口もご活用ください。
助産師会 相談窓口
https://www.midwife.or.jp/general/supportcenter.html
まとめ
いかがでしたでしょうか?赤ちゃんの体重や身長もぐんと成長し、赤ちゃんとの遊びも幅が広がる時期になります。
産後3ヶ月は、特にママの心身の健康にも気を付けたい時期です。子育ては、ストレスを感じて当たり前ですので、ひとりで抱え込まないことが大切ですね。
(文章作成:ひとで)
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。










