【1】読書通帳とは?
銀行ATMのような専用端末で読書履歴を管理できる!
 出典:www.uchida.co.jp
出典:www.uchida.co.jp読書通帳とは、銀行の預金通帳のように自分が借りて読んだ本の履歴が記載される記録簿のことです。
2010年に山口県の下関市立中央図書館で初めて導入されました。現在は全国で12の市町村が導入しています。
銀行ATMのような専用端末に読書通帳を通すと、自分が読んだ本のタイトルや貸出日を記録できる仕組みになっています。
通帳に記帳する仕組みを楽しみながら、読書意欲を高めようというのが狙いで、図書館によっては、システムの導入後、児童図書の貸し出しが2倍に増えたところもあるそうです!
ほとんどの自治体が無償で通帳は配布しています。
【2】読書通帳の作り方
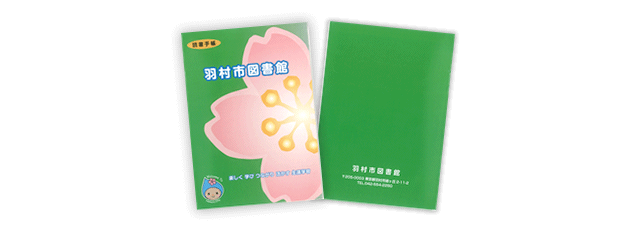 出典:www.hamura-library.tokyo.jp
出典:www.hamura-library.tokyo.jp読書通帳は大きく分けて、自分で記入したりシールを貼る手動タイプと機械で自動で印字をするタイプの2種類があります。
自分で記入するタイプの読書通帳は、図書館のホームページに掲載されている書式を自分で印刷して製本したり、図書館で登録をし、作成してもらうものがほとんどです。記入はすべて自分で手書きになります。
機械式の読書通帳は、図書館で身分証明書を提出し作成してもらいます。ほとんどの通帳には個人を識別するICチップがついています。写真のように機械により通帳に記録をしてくれます。
多くの自治体で、子どもは作成無料です。大人は無料、もしくは数百円程度の費用負担が必要な自治体もあります。今回は機械式の読書手帳についてご紹介して参ります。
【3】いろいろな読書通帳
①日本で最初に導入された読書通帳 下関市立図書館
 出典:www.minato-yamaguchi.co.jp
出典:www.minato-yamaguchi.co.jp山口県下関市の下関市立図書館は、日本で最初に機械式の読書通帳システムを導入しました。
書籍を借りた後、館内に設置されている専用の機械に通帳を差し入れると、貸出日や書籍名が印字される仕組みです。
中学生までは無料で通帳を作成することができます。宇宙をイメージしたデザインもかわいいですね!
この記事に関連するリンクはこちら
②浮いた本代が印字される読書通帳 海津図書館
 出典:www.asahi.com
出典:www.asahi.com岐阜県海津市図書館は、大垣共立銀行の協賛により「読書通帳」を導入しました。全国で6例目、東海3県では初の取り組みです。
こちらの読書通帳はなんと本のタイトルだけではなく、購入価格が印字されます。図書館で本を借りて読んだことにより、本代をどれくらい浮かせられたかが一目瞭然!
たまった金額を見て、にやにや楽しめそうですね。手帳のデザインもこぐまちゃんでかわいいですね。子どもの読書を推進するためにこの取り組みを始めたそうです。
この記事に関連するリンクはこちら
③豆のデザインがかわいい読書通帳 八尾市立図書館
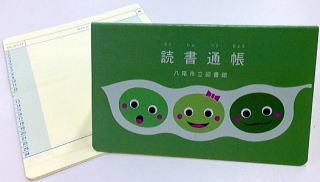 出典:web-lib.city.yao.osaka.jp
出典:web-lib.city.yao.osaka.jp2014年に関西では初めて読書通帳を導入した八尾市。小中学生には無償で通帳を発行していて、通帳を作りたくて図書館を訪れる子どもも多いんだとか。
本の貸出点数は、前年度の約3万9212点から8万1649点と倍以上に急増し、保護者からも大好評です。なお、大人は300円で手帳を作ることが可能です。
通帳のデザインも豆が描かれたかわいいもの。楽しみながら読書ができそうですね!
この記事に関連するリンクはこちら
まとめ
いかがだったでしょうか。子どもに読書を身近に感じてほしい、という目的のもとモデル事業として始まった読書通帳の取り組み。
子どもだけではなく、自分の読書履歴管理ツールとして、大人にも大好評です。読書通帳を活用して、子どものころからの読書習慣を大人になってからも続けるための『橋渡し役』として活用できたらいいですね。
まだ機械式の読書手帳を導入している自治体は限られていますが、手書き式読書手帳は自治体ホームページで提供しているところも増えているようです。
ぜひ、お子さんと一緒に読書記録を楽しみつつ、本を読むよろこびを感じさせてあげてくださいね。
子どもの読書の第一歩として、お子さんと一緒に一冊作ってみてはいかがでしょうか。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。







