大学の学費とは?総額は?

「大学の学費」とは一体、何で構成されるのでしょうか。
大学の費用といえば、授業料がまず頭に思い浮かびますが、入学料も大きなウェイトを占めてきます。
大学が国立なのか、公立なのか、私立なのかにもよって、授業料、入学料にはバラつきがあります。
入学料(平成29年度平均額)
・国立大学で282,000円
・公立大学で394,225円
・私立大学で252,030円
授業料(平成29年度平均額)
・国立大学で535,800円
・公立大学で538,294円
・私立大学で900,093円
になります。
これは、あくまでも様々な大学の平均額ではあるのですが、国立大学は授業料・入学料共に抑えられており、公立大学は国立大学に比べると入学料がやや高め、私立大学は入学料は抑えられているものの授業料がの額が高いことが分かります。
しかし、授業料は文系、理系、医歯薬系、芸術系などさまざまな学部によって大きな開きがあることも覚えておきましょう。
4年間の大学の学費(入学料+授業料×4年分)の目安は、以下の通りです。
国立大学・282,000円(入学料)+2,143,200円(535,800円×4年分)=2,425,000円
公立大学・393,618円(入学料)+2,153,176円(538,294円×4年分)=2,546,794円
私立大学・252,030円(入学料)+3,600,372円(900,093円×4年分)=3,852,402円
小さな金額ではありませんから、必要な時期に応じた準備が必要になりますね。
この記事に関連するリンクはこちら
私立大学の学費の特徴は?入学時に支払う金額は?
私立大学の学費は、学部や系統によって大きく異なるのが特徴です。また、授業料と入学料以外に施設設備費(約181,294円)などがかかることも。
ここでは、ある総合大学の学部を例に、入学時に支払う学費(初年度納入金)の差を見ていきましょう。
学費以外にかかる費用にはどんなものがある?

大学進学には、授業料・入学料以外の費用も必要になってきます。
まず、入学試験の時には、受験検定料が必要になりますし、入学時の各種保険料・教材費・交通費などの準備も必要です。
受験検定料は、受験する大学によっても、また、学部によっても大きく異なってきます。私立大学の医学部などは検定料も高額な場合がありますので、事前のチェックが欠かせません。
また、遠方の大学に通う場合には、一人暮らしをするための費用として、引っ越し代・敷金礼金・家財道具などの初期費用・仕送り金なども必要になりますから、国公立大学で授業料が低く抑えられても、家賃や仕送りなどを考えると近くの私立大学の方がコストが低かったのでは?というパターンも。
また、大学に入ってからアルバイトなどで生活費を用意しようと思っている、という方も多いのですが、実験実習などが多い学部学科に進学した場合は、アルバイトの時間がうまく取れない、ということもよくあるので、余裕を持った資金計画が必要です。
大学の学費を補助してくれる制度には何がある?
同じタイミングで大きな額を用意する必要がある大学進学。一度にこんな金額は無理…と思うかもしれませんが、保険などで子どもの小さいうちから準備したり、公的な補助や奨学金などを利用したりして、進学に備えることもできます。
子どもの進学に備えて、出来ることにはどんなことがあるのでしょうか。
学資保険
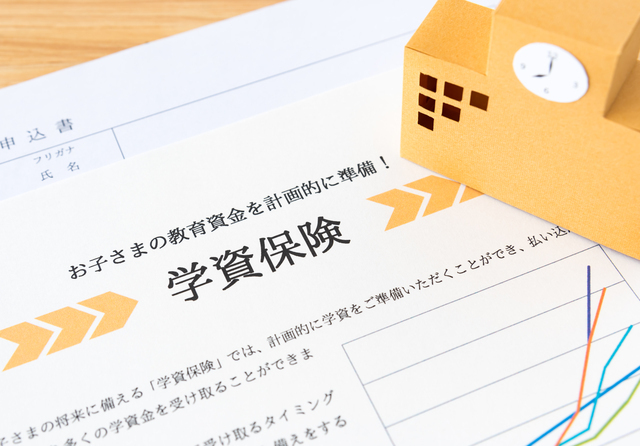
学資保険は、子どもが小さいうちに準備しておくことで、大学入学など、必要なタイミングでお金を受け取れる貯蓄型の保険。
妊娠中や赤ちゃんの頃から入れるプランも多く、早く始めて払い込みを早く終えれば、余裕を持って子どもの進学に備えることができますよ。
契約者である親が死亡したり、高度障害を負ったりした場合は、以後の保険料払い込みが不要になるものが多いようです。そのほかにも、病気やケガ、入院などに備える特約を付けられたりすることもあるので、保険内容とご自身の状況に合わせて契約することが求められます。
様々な保険会社の学資保険がありますが、配当があるもの無いもの、加入時期などによっても選ぶ学資保険が違ってきます。また、払い込みをする親の年齢や、子どもの年齢が高すぎると加入できないこともあるので、注意が必要です。
郵便局で手軽に入れるかんぽ生命保険の学資保険や、返戻率の高いソニー生命の学資保険、などが人気を集めているようです。
高等教育の修学支援新制度

大学・短大・高等専門学校、専門学校への進学を考えている人で、経済的な不安がある人には、2020年度から開始される国の高等教育の修学支援新制度というものがあります。
授業料などの減免(授業料と入学金の免除または減額)、給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金)の二つの支援があります。
この支援を受けるためには、世帯収入や進学先の学校の種類、自宅から通うのか一人暮らしかなど、さまざまな条件によって給付内容が異なってきます。
私立大学に自宅以外から通う場合は、給付型奨学金が年に約91万円、授業料が年に約70万円(上限)、入学金は上限約26万円の支援が受けられます。
申し込みは進学先の学校を通して、申請することができます。
奨学金

日本学生支援機構では、第一種(無利息)の奨学金、第二種(利息が付くタイプ)の奨学金、この二種類にあわせて入学時の一時金として貸与される入学時特別増額貸与奨学金(利息付)が用意されています。
無利息のタイプは「特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人」に貸与され、第二種は国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生・生徒が対象になります。
こちらは、国内の進学を目的としたものですが、海外留学を目的とした奨学金も用意されています。
いずれも、卒業後の返還が義務付けられており、月々決まった額を返還する定額変換方式、前年の所得もをもって、その年の毎月の返還額がきまる所得連動変換方式の2種類の返還方式が選べるようになっています。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)

教育一般貸付と言われる国の教育ローンを利用する方法もあります。
奨学金は子どもに与えられるものですが、教育ローンの場合は、返済能力のある親に貸し出しされることが多い、という点が大きな違いです。
日本政策金融公庫が取り組んでいる、教育一般貸付は、最高350万円までの借り入れが可能で、固定金利年1.66%が設定されています。受験前でも申し込みが可能なので、入学料などを目的に活用することもできます。また、海外留学の場合は、最高450万円までの借り入れができますが、世帯年収の限度などもありますので、注意が必要になります。
母子家庭、父子家庭、交通遺児家庭や子ども3人以上の一部世帯、世帯年収200万円以内の場合などは金利の優遇や返済期間の長期設定、保証料の減免などが受けられる場合もあります。
この記事に関連するリンクはこちら
まとめ
いかがでしたか?大学進学には、授業料、入学料のほかにも様々なお金が必要になることがお分かりいただけたでしょうか。
こうした資金は、家計に余裕があると思っているおうちでも、一度に用意しなければならないとなると、大きな負担になるもの。子どもが小さい時から準備できる学資保険などを上手に活用して、将来に備えてあげたいものですね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。











