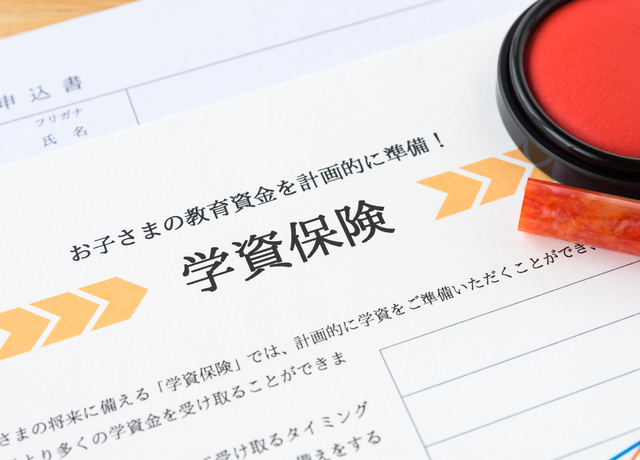目次
この記事に関連するリンクはこちら
学資保険ってそもそも何?
子どもにかかる費用って?(幼稚園から高校まで)
それでは、子どもにかかる教育費について説明しましょう。平成28年度の子どもの学習費調査によると、幼稚園(3歳)から高校まですべて公立だった場合にかかる教育費は、15年間で約540万円です。
一方、幼稚園(3歳)から高校まですべて私立だった場合にかかる教育費は、15年間で約1,770万円にもなります。
更に学校外活動費として、スイミングなどの習い事や塾などの費用を加算すると子ども1人にかかる教育費は非常に高額になります。
学資保険は必要?おすすめする理由とは?
資金計画が立てられる
学資保険のメリットの1つめは、毎月もしくは年払いで計画的に資金を貯められることです。学資保険の保険料の払い込み方法は、月払いもしくは年払いが一般的です。
もしものための保障がある
学資保険のメリットの2つめは、もしもの時の保障があることです。
学資保険は一般的に両親のどちらかが契約者、子どもが被保険者になります。契約者に万が一のことがあった時には、その後の保険料の支払いが免除されます。そのため、契約者は、一般的には家計の中心者がなることが多いです。
貯金が苦手な人におすすめ
学資保険のメリットの3つめは、貯金が苦手な人でも教育資金が貯められるという点です。
学資保険で最も多い保険料の支払い方法は、 月払いです。月払いの場合、毎月決まった日にちにお金が引き落とされるので、ある意味強制的にお金を貯めることができます。
学資保険のデメリット
年齢制限がある
学資保険のデメリットの2つ目は、学資保険の加入には年齢制限があることです。学資保険に加入したくても年齢制限にひっかかってしまうと、当然ですが学資保険に加入することは出来ません。
大学受験や入学金に学資保険を充てることが出来ない可能性がある
学資保険のデメリットの3つ目は、大学受験や入学金に学資保険を充てることが出来ない可能性があることです。
学資保険は 18歳時点で満期資金が入金になるものが一般的です。しかし、最近の大学の入試形態は、推薦入試やAO入試など多岐に渡っています。入学金を払うタイミングによっては学資保険の満期資金を学費の支払いに充てることが出来なくなってしまいます。
学資保険はいくらくらい払うもの?月々の支払金額は?
各家庭の教育プランや財政状況による
学資保険の月々の支払額ですが、ケースバイケースとしか答えることが出来ません。預貯金に回せるお金は、各家庭によって異なりますし、子どもが公立、私立によってかかるお金は異なってきます。各家庭の教育プランや財政状況によって適切な保険料を決めるようにしましょう。
学資保険を選ぶポイント① 配当金
学資保険を選ぶ際のポイントの1つ目は、配当金が出るかどうかです。
学資保険の中には、配当金が出るものがあります。配当金が出るとうれしい気持ちになります。しかし、あくまでもトータルでいくらプラスになるかが最も重要なことになります。配当金の有無に惑わされないことが重要です。
学資保険を選ぶポイント② 還元率
学資保険を選ぶ際のポイントの2つ目は、還元率です。
満期の際に何%増えているかは学資保険を選ぶ際に最も重要なポイントです。また、解約時の返戻率も重要になります。学資保険は基本的に解約することはないと思いますが、もしそうなった時に、解約返戻率も重要になることは考慮しておきましょう。
学資保険を選ぶポイント③ 受取人
学資保険を選ぶ際のポイントの3つ目は、受取人を誰にすればいいかのかという問題です。
子どもの学費のために学資保険に入るので、子どもが受取人になるのではないかと思われる方もいるかもしれません。しかし、学費を払うのは一般的に親になるかと思いますので、受取人も親にするのが一般的でしょう。
また、学資保険の受取人は契約しているパパかママにするようにしましょう。
契約者=パパ、被保険者=子ども、受取人=ママにしてしまうと贈与税がかかってしまい、契約者=受取人の場合に比べて税金が高くなってしまう可能性が高いからです。
契約者=受取人の場合にかかる税金は、所得税の中の一時所得になります。一時所得は、(保険金-50万円)÷2 で計算されるので贈与税に比べてお得な税金になります。
学資保険を選ぶポイント④ 生命保険料控除
学資保険を選ぶ際のポイントの4つ目は、年末調整などの控除があるのかということです。
学資保険には、生命保険料控除が適用になります。年末調整の控除の対象になるので契約者は家計の中心者がなる方が良いかと思います。
専業主婦など収入がない人が学資保険の契約者になってしまうと生命保険料控除の恩恵を受けることが出来なくなってしまうからです。
まとめ
学資保険は子どもの学費を貯める最も一般的な諸金融商品になります。ぜひ、今回説明したポイントを理解して、ご自身に合った学資保険を選んでくださいね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。