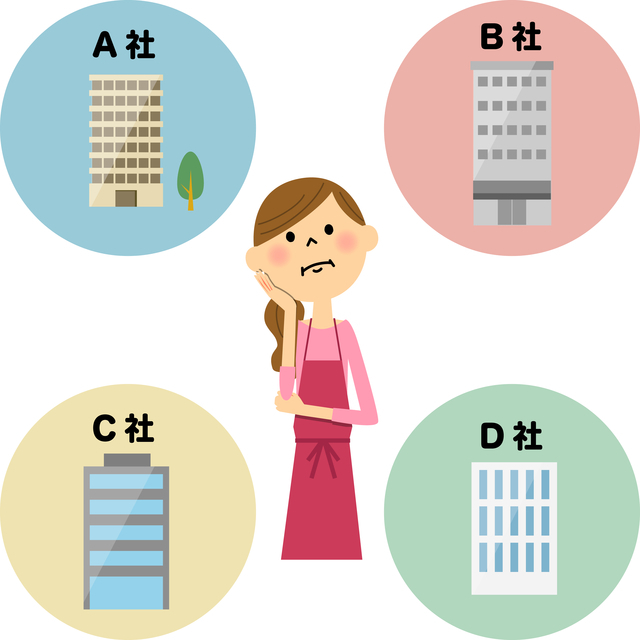目次
この記事に関連するリンクはこちら
そもそも学資保険ってどんなもの?

学資保険は、大まかにいうと「将来必要となるであろう子どもの教育資金を準備できる保険」です。特徴としては、
・好きなタイミングでお金を受け取れる
・契約者(主に親)に万一のことがあったら支払免除で保険金が受け取れる
・税金がかからず受け取れる場合がある(例:一時所得なら50万以下)
・特約で医療保障が付けられる商品もある
などが挙げられます。
「お金を貯めるだけなら定期預金でもいいんじゃない?」とも思いがちですが、将来必要だと分かっていてもなかなか貯められないものです。つい後回しにしてしまったり、目先のことに使ってしまったりすることもしばしば。
学資保険というしくみを使えば、毎月、いわば強制的にお金を貯めることができます。さらに途中解約してしまうと元本割れするものがほとんどです。お金の管理が苦手な方にはぜひ利用してほしいしくみといえるでしょう。
①貯蓄性の高い商品を選ぶ
学資保険は基本的に貯蓄性の高い保険だといわれています。
各保険会社から様々な商品が出ていますが、「教育資金を貯める」というニーズが大きいため、利率が固定されている元本保証タイプの商品が多いし人気となっています。
中には利率が変動され元本保証のない商品もあります。このようなタイプは景気状況によっては満期保険金などに大きな増え幅がある分、元本より減ってしまう可能性もあるため、きちんと理解して選ぶようにしましょう。
②満期の設定を慎重に
学資保険は「子どもが◯歳になる時に満期学資金を受け取る」と決めることができます。しかし、何歳でいくらくらいに設定すればいいのか悩む方が多くいます。
学資保険は子どもが小さいうちに入る場合がほとんどで、まだ進学なども具体的には考えられないですよね。
一般的に、育資金がまとまって必要になるピークは「大学入学時」と言われています。授業料や入学金、さらには下宿する場合など、諸経費も多くかかります。
金額は一般的に、私立大学の入学金平均113万円+その他(複数の大学の受験費・交通費・滑り止め大学の入学金など)で200万~300万前後目安に設定する方が多いです。そのため、多くの人が高校卒業前の17.18歳前後に満期を設定しています。
他には、小、中、高の入学時に「一時金(祝い金)」を受け取れるようにする方法もあります。
小学受験、中学受験などを検討している方にはおすすめですが、注意点として忘れてはいけないのが、節目節目でお金を受け取っていると満期時にもらえる総額が低くなってしまう点です。
さらに、2020年4月から私立高校の授業料の実質無償化が全国でスタートされたり、大学進学時の奨学金などを対象者・金額ともに大幅拡充するなど、教育資金の負担が軽減されるような政策もあります。
やはり大学入学時を目安に満期を設定するのがスタンダードといえるのではないでしょうか。
学資保険は、満期後も長く運用すればするほど増えていく保険です。そういった特徴も踏まえて、ひとまず大学入学時まで、を目安に運用する方法を選ぶ方が多くなっています。
さらに実施満期の設定は、お子さんの生まれ月などによって。受け取れるタイミングが微妙に違ってきます。契約時にしっかりシミュレーションを作成し検討してみると良いでしょう。
③「返戻率」の高い学資保険を選ぶ
学資保険を選ぶ際に最も大きなポイントとなるのは返戻率です。「支払い(予定)の総額」に対する「受け取る保険金の総額」の割合を「返戻率」と呼びます。つまり払った額に対してどれだけ増えて戻ってくるか、を表す割合です。
さらに、同じ保険でも保障内容や払込期間によって返戻率は変わってきます。
2019年10月時点での返戻率は103~108%位のものが多いようです。見積もりを出してもらう際には必ずチェックし、いくつか比較して、その他条件が同じであれば高いものを選びましょう。
④元本割れする商品に注意
しかし、2018年からマイナス金利の影響で、返戻率はどんどん低下する傾向にあります。現在高い返戻率の商品でも、時間が経てば経つほど販売停止や返戻率低下の可能性が大きくなります。近年では元本割れしてしまう商品も実際にあります。
返戻率は高いほうがいい!と考える方は、なるべく早くにお近くの金融機関に見積もり・相談に行くことをおすすめします。
元本割れしている商品は、確かに返戻率だけを見ると魅力的ではありませんが、月々の保険金が安い・保障が手厚い・加入時の審査が緩いなど、他の商品にはない特徴を持つ場合があります。
気になる商品の返戻率がイマイチでも、一度見積もりや相談だけでもしてみる価値はあるかも知れません。
⑤医療保険特約が必要か考えて
学資保険は医療保険特約を付与することができるものが多いです。
ですが前節でお伝えしたとおり、この特約を付けることで元本割れを起こしてしまうリスクがあります。
さらに、お住まいの自治体によっては、中学生以下の子どもの医療費が無償であったり助成が受けられるなど、そもそも医療保障が必要ではない場合もあります。
ですので医療保障を付けないで契約する人が多い傾向にあります。貯蓄性を重視した保険の場合、初めから特約がないものもあるくらいです。
ただ、長期入院など大きな病気をしてしまった場合の差額ベッド代や通院のタクシー代などは実費で賄う必要があります。医療費助成だけでは不安な方がいれば検討してみてもよいでしょう。
①返戻率をチェック
前節でお伝えしたように、その他条件が同じであれば返戻率はなるべく高いものを選びましょう。
②必要なプランを組んでくれるか
学資保険に何を求めているか、をきちんと整理し、それに沿ったプランの保険かどうか見極める必要があります。例えば、貯蓄性の高い学資保険を求めている場合は、不必要な特約が付与されていないか、などをきちんと見て契約しましょう。
③払込期間は適切かチェック
学資保険は、◯歳までに必ず満期がくるように、など、払込期間がある程度決められている場合があります。
どのタイミングで満期保険金を使うつもりなのか、などを具体的に決め、それに沿った商品を選ぶようにしましょう。
④支払い金額に無理はないかチェック
毎月の支払い金額が多くなりすぎていないかチェックしましょう。世帯の収入や貯蓄状況などは人それぞれ違います。月々の負担が大きい場合は払込期間を調整するなどをして、無理のない支払い計画を立てましょう。
⑤少しでもお得になる方法とは?
少しでもお得に契約するにはどうしたら良いのでしょうか。ポイントは返戻率を少しでも上げるように工夫することです。
⑥年払いにする
学資保険は基本的に払込期間を短く、まとめて支払うことで運用期間を長くした方がより返戻率を高めることができます。まとまった資金が準備できる場合、全期前納支払いにしても良いでしょう。
⑦子どもが小さいうちに払い込む
子どもが小さく、まだそれほどお金がかからない時期に加入して、なるべく短期間で支払いを終えてしまうのもおすすめです。商品によっては妊娠中から加入できるものもあります。また、加入が早ければ早いほど、満期までの時間が長く取れるため、月々の支払い金額が低く抑えることもできます。
まとめ
まず大切なのは、ご家庭で「学資保険に求めるもの」をはっきりさせることです。
そのためには、いつにいくら必要になるかは、しっかりと把握しておく必要があります。分からなければ、積極的に金融機関の無料相談などに参加して、色々聞いてみるのが良いでしょう。
子どもにかかるお金は、成長ステージによって大きく変わります。少しでも学資保険に興味を持っていただき、計画的に備えてお金の不安を解消して子どもの成長を楽しんでくださいね!
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。