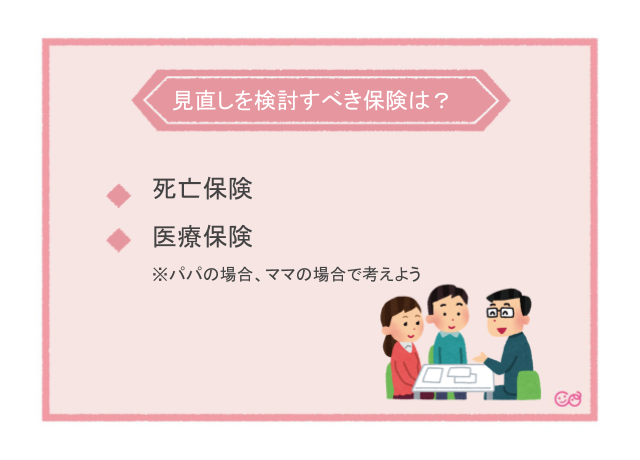目次
妊娠~出産時に生命保険・医療保険は使える?
妊婦健診にかかるお金
妊娠した人が定期的に受ける健診は、本来は公的保険の対象外です。
妊婦健診に限らず、「健康診断」は治療ではないので保険の範囲外とされているからです。同じ理由で、民間の医療保険で保障されることもありません。
しかし、健康に赤ちゃんを産んでもらうために妊婦健診は欠かせないもの。そのため、現在は自治体から最低14回分の妊婦健診費用が助成される仕組みになっています。
具体的には各市町村から妊婦健診費用の「補助券」が発行され、多くの場合、母子手帳の交付と一緒に配布されています。補助券で助成される額は自治体によって異なりますが、平均的には1回あたり1万円程度が助成されます。
入院や出産・分娩にかかるお金
分娩のための費用も、基本的には保険対象外であり、医療保険も使えません。妊娠同様それ自体は病気ではないからです。
ですが、公的保険から、出産育児一時金というお金をもらうことができます。
子ども1人につき、原則50万円が支給されます。通常は病院に直接支払ってもらう手続きをとり、分娩・入院費用で自費負担するのは出産一時金を差し引いて残った額だけになります。分娩・入院費用が50万円未満だった場合は差額を受け取れます。
帝王切開にかかるお金
分娩の費用は保険対象外ですが、帝王切開など自然分娩でない場合は、医療的な処置を行ったということで保険が適用されます。
自己負担はかかった費用の一部で済みますし、費用が高額になってしまった場合は高額療養費制度の対象にもなります。
高額療養費制度とは、所得額に応じて、月あたりに一定以上の医療費がかからず、超えた分は払い戻されるという制度です。
医療費の保障をしてくれる医療保険なども、帝王切開であれば対象となる場合が多いですが、保険の契約内容によって異なる場合がありますので、確認しておきましょう。
なお、ここまでご紹介した健診費や自然分娩での分娩費も含めて、妊娠・出産に関する費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、年間にかかった医療費の額に応じて所得が差し引かれ、結果的に課される所得税・住民税が少なくなる仕組みです。医療費控除は確定申告で手続きを行えます。
妊娠がわかってから生命保険には入れる?

帝王切開になった場合は、医療保険で保障されることがあるとお伝えしました。
帝王切開になると自然分娩よりも多くの費用がかかりますから、保険でお金が受け取れれば助かります。だったら「保険に入っておこう」と思った方もおられるかもしれません。ですが、妊娠してから保険に入れるのでしょうか?
残念ながら、妊娠がわかってから新たに保険加入することはできない場合がほとんどです。入れたとしても、「不担保」といって、妊娠に関連する内容は保障されないという契約になります。
この場合は、加入して帝王切開だったとしても結局、保障されないことになってしまいます。
しかし、次回以降の出産に備えてや、出産後の自分の病気のことを考えると、不担保だとしても入れるときに入っておく意味はあるでしょう。(なお、一度帝王切開を経験すると、次回以降も原則帝王切開となるため、出産については不担保になる場合が基本です)
妊娠したら見直しを検討すべき保険は?
死亡保険
死亡保険は、誰かにもしものことがあってその人が亡くなった場合、残された人に保険金が支払われるという形の保険です。
例えば、夫の収入で暮らしていた妻は、夫が亡くなって収入が途絶えると、その後の生活に困ることになります。そこで、夫が死亡保険に加入していれば、保険金で妻の生活を支えることができます。
【死亡保険の種類】
定期保険:保障が一定期間
終身保険:保障が一生涯続く。解約すると払い込んだ保険料が戻ってくる仕組みのため、資金づくり(貯蓄)のために利用することもできます。
パパの死亡保険
パパの収入を中心に生活している家庭では、万一の場合に残される家族のため、死亡保険は必須です。しかし、保険金額が多いほど保険料も高くなるため、過不足のない保険金額(保障額)で契約したほうがいいでしょう。
子どもがいると、親が亡くなって子どもが残された場合の子どもの生活費や教育費も考える必要があります。
すでに保険に入っている場合も、子どもができたぶん保障額をアップさせなくてはならないので、保険の内容を見直すべきです。
パパが亡くなった時点で18歳未満の子どもがいる場合、ママは社会保険制度から「遺族年金」を受け取ることができます。死亡保険の保障は、遺族年金を受け取っても足りないぶんを補う額に設定することで、「保険の掛けすぎ」を防げます。
また、必要な保障額は子どもが小さいほど多額が必要で、子どもが大きくなるにつれ、減っていきます。子どもが独立するまでの期間が短くなるためです。
そのため、常に多額の死亡保障がいるわけではなく、子どもが小さい時期だけ定期保険に加入したり、保障が必要な期間を考慮して受け取れる収入保障保険などを検討すると良いでしょう。
死亡保険に加入していても、さいわい万一のことがなければ、子どもの独立を見届けられます。子どもを扶養する必要がなくなれば、死亡保険もその役目を終えることに。
そのとき、終身保険など貯蓄性のある保険に加入していれば、保険を解約して解約返戻金を受け取り、自分の老後資金として活用することができます。子どもの結婚資金の援助をしたり、住まいのリフォーム資金にしてもいいでしょう。
終身保険は貯蓄性のない「掛け捨て」型の保険(定期保険など)に比べると保険料が割高ですが、貯蓄のかわりに、死亡保障を確保しながら老後資金を準備するという方法もあるのです。
ママの死亡保険
ママには死亡保険は不要でしょうか?結婚前に加入している保険がそのままだという人もいるかもしれませんが、解約したほうがいいのかなどを検討してみましょう。
共働きか、専業主婦かでも考え方が違ってきます。
【共働きの場合】
死亡保険は、その収入で家族を支えている人に必要なものです。
パパの収入が中心の家庭でも、共働きでママの収入がないと困るような状態なら死亡保険は必要と言えます。
【専業主婦の場合】
残された家族の生活費という意味では問題ないのですが、ママが亡くなった後、パパが子どもを育てていくことを想像してみてください。
家事や子育てのためにお金を払ってサポートを頼む必要があるかもしれませんね。そのお金を貯蓄から出すのが厳しければ、ママがなくなったときにも保険金を受け取る意味はあります。
子どもが小さいうちだけでも、死亡保険に加入したほうがいいかもしれません定期保険であれば、一定期間だけ安価に保険に加入できます。
ママの老後資金の準備として、貯蓄性のある死亡保険に加入することも検討してみましょう。
考え方としてはパパの場合と同じです。また、専業主婦の期間が長いと、もしも離婚してしまった場合、老後に受け取れる年金額が、自分で働いていた人に比べて少なくなってしまうため、老後資金を備えておく意味もあります。
ただし子育て中は共働きのママも仕事ができず、世帯の収入が低下します。ムリのない保険料で加入するよう注意しましょう。
医療保険
医療保険は病気やケガで医療費がかかってしまった場合に備える保険です。
入院した場合に、入院日数に応じて給付金を受け取れる保障が代表的。ほかにも手術や通院に対する保障など、さまざまな保障を揃えた商品が各社から販売されています。
【医療保険の種類】
定期タイプ:保障が一定期間だけ。若いうちに加入すると保険料は安いですが、入り続けるためには更新が必要で、更新のたびに保険料は上がっていきます。
終身タイプ:保障が一生涯続く。保険料が高めですが、加入後ずっと保険料が変わりません。
医療保険はごく一部を除いて、解約しても保険料が戻ってこない掛け捨てタイプが主流です。
パパの医療保険
家族の収入がパパを中心にしている場合、パパが入院して収入が低下することは大きなリスクです。もちろん入院そのものにも費用がかかります。公的保険で保障される部分もありますが、医療保険に加入していればそれ以上の出費があっても貯蓄を減らさずに済むでしょう。
とはいえ、子どもが生まれたら、教育資金準備や子育て費用になにかとお金がかかるもの。そのうえ保険料を払って家計にムリがないか、総合的に考えて検討することが大事です。
また、医療保険は商品によって保障内容に幅があるので、よく比較して検討しましょう。
ママの医療保険
ママの入院は、費用の面もさることながら、家事や育児の手がなくなるので困るという家庭も多いでしょう。その意味で、専業主婦だから保険が不要とは言い切れません。女性は年齢が上がるにつれ、女性特有の病気の心配も増えてきます。特に、男性はがんのリスクが40代以降に増え始め、50代からぐんと高くなるのに対して、女性は30代からゆるやかにリスクが上がり始めます。
そこで、女性特有のがんを含めた、女性疾患への保障を手厚くした医療保険も販売されています。
パパの場合と同じく、保険料と保障内容、家計の状況を考えて検討しましょう。
【参考:コズレ調査】先輩ママパパは妊娠を機に保険を見直したのはなぜ?
妊娠中にFPに相談をおすすめします
出産したら慌ただしくなるから今のうちが吉!
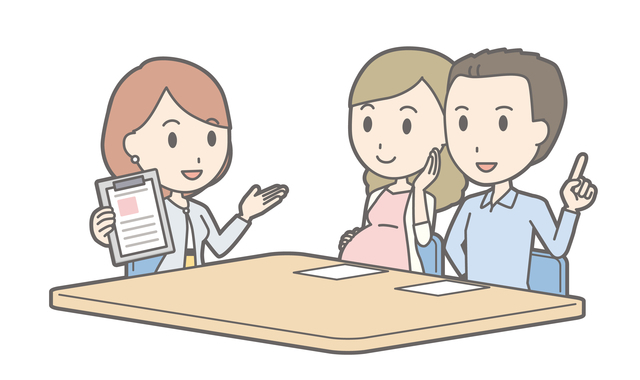
妊娠・出産と保険について見てきました。
妊娠・出産は、保険の見直しについて絶好のタイミングと言えます。子どもが生まれることで、新たに保障が必要になるという意味でもそうですが、出産後は忙しくて保険についてじっくり考える時間をとるのが難しいです。
そのため、妊娠中の比較的余裕のある時期に、現在加入中の保険をチェックする、保険商品の情報を集めるといった作業をしておくことをおすすめします。
普段なじみのない保険について、考えるのが難しいという場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみましょう。加入している保険証券を見てもらって問題がないかチェックしてもらったり、適切な保険のアドバイスをもらうことができます。
まとめ
妊娠・出産のタイミングでは、保険の見直しをしたほうがいいということをお伝えしました。
パパの死亡保険はもちろん、ママにも死亡保険があったほうがいい場合もありますし、死亡保険だけでなく医療保険にも検討の余地があります。今すでになにかの保険に加入している人も、保障内容が適切か見直しをしてみましょう。
自分で見直すのが難しい場合は、FPのアドバイスを取り入れるのがおすすめです。お子さんが生まれて忙しくなるまえに、必要な保険をしっかりと確保しておいてください。(執筆:リキオ)
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。