【1】お腹にいた時と似たような環境を作ってみる
おくるみやCカーブクッションなど
 出典:www.amazon.co.jp
出典:www.amazon.co.jpそもそも離乳食開始前の赤ちゃんは少なくとも3~4時間ごとに授乳が必要となり、離乳食開始前に夜中通して寝る赤ちゃんは珍しいようです。
ただ、夜中に授乳した後にそのまま寝てくれるかどうかで、親の翌日の疲労度が違います。
授乳後に覚醒してしまわない方法としては”おくるみ”や”トッポンチーノ”(伊モンテッソーリのおくるみ)で包む、Cカーブ授乳クッションで授乳してみるなどがあります。
”おくるみ”は身体を包むことで安心感をあたえ、”Cカーブ授乳クッション”は新生児の脊髄の形にあわせることで背中スイッチを軽減します。
また、お腹にいた時の環境という意味では、胎内音が聞けるぬいぐるみやCDをかけてみても良いかもしれませんね。
※背中スイッチ・・・抱っこで寝ていたもしくは機嫌よくしていた赤ちゃんをベッドなどに置いた瞬間、泣きだしてしまうこと。
今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら
【2】ねんねトレーニング
赤ちゃんに生活リズムを教えてゆく
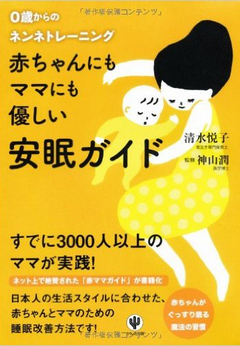 出典:www.amazon.co.jp
出典:www.amazon.co.jp次に実践してみたいのが、「安眠ガイド」に代表されるような、いわいるネンネトレーニング。
こちらの清水悦子さんの著書をはじめ、ジーナ・フォードさんのカリスマ・ナニーが教える赤ちゃんとおかあさんの快眠講座が有名です。
授乳感覚をあける、朝には太陽の光をあびさせるなどして、赤ちゃんに生活リズムを教えてゆきます。
ただ当然ですが、これらを実践してすぐにうまくいく場合と、全くうまくいかない場合があるようです。
全て本どおりに実践しようとして、お世話する人が疲れすぎてしまっては本末店頭。一つの知識・考え方として、無理のない範囲でやってみるとよいかもしれません。
今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら
【3】あやし方を工夫してみる
ママの産後ケアとエクササイズをかねてバランスボール
 出典:madrebonita.strikingly.com
出典:madrebonita.strikingly.comママたちの産前産後のケアとエクササイズを提唱するNPO法人マドレボニータ。
全国13都道府県にお教室があり、産後1ヶ月から赤ちゃん同伴で参加できます。
こちらの特徴は有酸素運動をバランスボールを使って行うこと。また、赤ちゃんが泣いたときは抱っこしながら運動を行います。
教室で抱っこしながら運動していると、バランスボールの揺れが気持ちいのか、寝てしまう赤ちゃんも続出!
私も教室修了後は自宅にバランスボールを買い、バランスボールに座りながら授乳をしたりテレビを見たりしていました。
バランスボールはあくまでも”あやし方”の工夫のひとつ。
このほかにも、抱っこひもにいれて歩く、車でドライブするなど色々あるので、一番あうものを探してみてください。
※身体がまだ未熟な赤ちゃんは強く揺らすと大変危険です。必ず、専門家の指導のもと行いましょう!
今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら
【4】寝ないものとあきらめる
寝ない前提でパートナーと話し合いを
 出典:PIXTA※写真はイメージです
出典:PIXTA※写真はイメージですこれまで、環境を整える、ねんねトレーニングしてみる、あやし方を工夫してみると3つご紹介しましたが、最後は「あきらめる」です。
身も蓋もないですが、寝ない赤ちゃんをどうにか寝かせようとすることは、意外と精神的に消耗するものです。
逆転の発想で、赤ちゃんはもう寝ないものとしてパートナーと話し合ってみてはどうでしょうか?
内容は「どう分担するか」「分担が無理なようなら睡眠をどう確保するか」などです。
赤ちゃんと長い時間いる人が疲れすぎてしまわないことが赤ちゃんのためにも大切です。
パートナーや実家、どちらも無理のようなら行政や保健所に相談してみましょう。
まとめ
いかがでしたか?
先日、4人を育てた先輩お母さんが言ってました。
これなら絶対うまくいくなんて方法はない。子どもが違えば違うし、同じ子でも時期が違えば違う。「あまり1つにこだわらず、常に新しいカードを試してみることね」
お~~~!と思わず声を上げてしまった目からウロコの子育て論でした。
10人の赤ちゃんがいれば、10人の個性があります。心配なほどミルクも飲まず寝こけてしまう赤ちゃんや、逆に全く寝ない赤ちゃん。。
大丈夫です。子どもが大きくなり、いつかは必ず寝られる日が来ます。
なるべくゆったりとした気持ちで赤ちゃんを見守れるといいですね。
この記事に関連するリンクはこちら
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。






