乳幼児医療費助成制度とは
乳幼児医療費助成制度の対象者は?
対象となる条件
乳幼児医療費助成制度の対象になる子どもは、下記の通りです。■保護者が対象の自治体に住所を持っている
例えばA市に父・母・子どもの3人で住んでいて、父が申請者だとします。
ある日父が単身赴任でB市に引っ越し、母と子どもがA市に残ったという場合には、母を申請者にする必要があります。
■子どもが健康保険に加入している
子ども自体が、親の健康保険の扶養に入っており、健康保険に加入している必要があります。
■年齢は自治体により異なる
対象外になるケース
対象外になる子どもは、下記の通りです。■健康保険や国民健康保険に加入していない
会社や役所への手続きを忘れていて、子どもの健康保険証が手元にないという人は、要注意です。
■生活保護を受けている
生活保護世帯は元から医療費負担が無いので、対象外になります。
■施設に入所、里親の元にいる
児童福祉施設や里親の元で育てられている子どもは、対象外です。
また強制的に入所となる「措置入所」の場合も、対象外になります。
乳幼児医療費助成の範囲は?
乳幼児医療費助成制度の助成範囲は、保険適用ができる治療・入院費・薬代に限定されており、その中での助成対象範囲は自治体により異なります。
どの自治体でも、下記のケースでは対象外になるので、注意が必要です。
■交通事故などで、第三者から受け取った保険金と重複する分
■高額医療費との重複分
■総合病院や救急病院を利用した際の、初診の特定療養費
また薬局によっては、軟膏などを入れる容器代は対象外となることがあります。
助成額はいくら?
助成額は自治体によって下記のようなパターンがあるので、詳しくはお住まいの自治体に確認して下さい。
■医療費全額を負担
全額負担とは言っても、お住まいの自治体にある医療機関のみとする自治体もあれば、別の地域の医療機関での費用も負担してくれる自治体もあります。
■医療費の一部を負担
一定額を差し引いて負担する自治体もあります。
■所得制限
所得制限を設けない自治体もあれば、一定の所得制限を設ける自治体もあります。
乳幼児医療費助成制度の手続き方法
①赤ちゃんの出生(戸籍)手続きをする
赤ちゃんが生まれたら、お住まいの自治体の役所で、出生(戸籍)手続きを行います。
これを行わないと赤ちゃんの住民登録ができないので、乳幼児医療費助成制度の申請自体ができません。
また、出生手続きは14日以内に行う必要があります。
②赤ちゃんの健康保険の加入手続きをする
次に、赤ちゃんの健康保険の加入手続きをします。
パパかママが会社員の場合(2人とも会社員の場合には年収の高い方)には、会社の担当者に伝えて手続きをしてもらいます。
パパもママも会社員ではない場合は、赤ちゃんは国民健康保険に加入するので、役所で手続きをしてもらいます。
③赤ちゃんの健康保険証が届く
健康保険の手続きが終わると、赤ちゃんの健康保険証が後日届きます。
時期によっても異なるので、申込時にだいたいどれくらいで届くかについて、確認しておくと良いでしょう。
④乳幼児医療費助成制度の申請をする
届いた健康保険証を持参し、お住まいの自治体の窓口で「乳幼児医療費助成制度」の手続きを依頼します。
保険証が手元に無い場合でも、自治体によっては先に手続きを進めてくれるところもあります。
この場合は、保険証が届き次第コピーを提出します。
申請に必要なもの
申請に必要なものは、下記の通りです。(自治体により異なることがあります。)■乳幼児医療費助成申請書
■健康保険証
■印鑑
■申請者とその配偶者のマイナンバーカード(又は個人番号通知カード)
■本人確認書類
乳幼児医療費助成申請書については、ほとんどの自治体でホームページからダウンロードすることが可能です。
また書き方も掲載されていることが多いので、記入漏れや不備を防ぐために、あらかじめ確認をしておくと安心だと言えます。
コズレオリジナル「出産後の手続きリスト」をチェック!
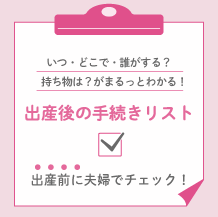 出典:feature.cozre.jp
出典:feature.cozre.jpご紹介したように、乳幼児医療費助成制度の申請をする前に、様々な手続きが必要となります。
手続きに行ったけれども必要なものを忘れて申請できなかった…
ということのないように、コズレオリジナルの「出産後の手続きリスト」を使ってチェックしてみてくださいね!
乳幼児医療費助成制度の利用方法
医療機関の窓口で助成が受けられるケース
1つ目は、医療機関の窓口で助成が受けられるケースです。
簡単に言うと、自己負担金がなく、お金を用意しないで治療や薬をもらうことができるということです。
病院や診療所などの医療機関の窓口で「乳幼児医療証」を提示すると、医療機関の方で自動的に処理手続きを行ってくれるので、その場で助成を受けることが可能です。
後日償還払いを受けるケース
2つ目は、後日償還払いを受けるケースです。
簡単に言うと、一旦自己負担金として全額支払い、後日返金してもらうということです。
病院や診療所などの医療機関の窓口で、一旦全額支払います。
そこでもらった領収書を必ず保管しておき、後日その領収書と申請書を役所に提出します。
申請受理後に指定の口座に返金されるという流れです。
乳児医療証がまだ届いていない場合
乳幼児医療費助成制度を受ける為の手続きを行ったけれども、まだ乳幼児医療証が手元に届かない場合もあるでしょう。そんな時に、子どもが病気やケガで医療機関を受診したとします。
その場合には、一旦医療機関の窓口で自己負担金を全額支払い、その時にもらった領収書を保管しておきます。
後日乳幼児医療証が手元に届いたら、領収書も持って役所に行き、返金手続きをしてもらいます。
病院によっては、柔軟に対応してくれる場合もあるため、事前に確認してみましょう。
乳児医療証を忘れて受診した場合
乳幼児医療証自体は手元に届いたけれども、医療機関を受診する際に、持っていくのを忘れてしまうこともあるでしょう。その場合も、一旦医療機関の窓口で自己負担金を支払う必要があります。
後日役所に領収書と乳幼児医療証を持っていき、返金手続きをしてもらいます。
返金されるまでに時間がかかるので、乳幼児医療証を忘れた場合には、自宅が近い場合には取りに帰ったり、ご家族に医療機関まで届けてもらったりするなどの方法を取ると良いでしょう。
お住まいの自治体以外の医療機関を受診した場合
お住まいの自治体外の医療機関を受診した場合は、一旦自己負担が発生することがあります。ただし、お住まいの自治体が「他の自治体の医療機関を受診した場合も助成する」という場合に限ります。
この場合も、後日役所に領収書と乳幼児医療証を持っていき、返金手続きをしてもらうことになります。
その為、特にこだわりや緊急性が無ければ、自治体内の医療機関を受診する方がスムーズだと言えます。
償還払いの手続きの仕方
償還払いはお住まいの自治体の役所で手続きをしてもらいますが、その際には下記を持参しましょう。■乳幼児医療証
■金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
・申請者名義のものです
■医療機関でもらった領収書
■高額療養費等の給付金の支給決定通知書
・もらっていない人は持参不要です
■健康保険証
・お子さんのものです
■払い戻しの申請書
・役所の窓口でもらうことも可能です
自治体により細かい部分は異なりますし、1年以内に手続きをする必要があるので、注意しましょう。
まとめ
子どもはケガや病気をすることがよくあります。
そのたびに受診代や薬代を払うと、積もり積もると結構な金額になるので、自治体が負担してくれるのはとてもありがたいことだと言えます。
ただし手続きをして乳幼児医療証を手に入れる必要があるので、お子さんが生まれて出生届を出して保険証をもらったら、早めの手続きが肝心です。
後日償還の場合も、指定口座に返金されるまでに時間がかかるので、なるべくその場で助成が受けられるように意識すると良いでしょう。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。










