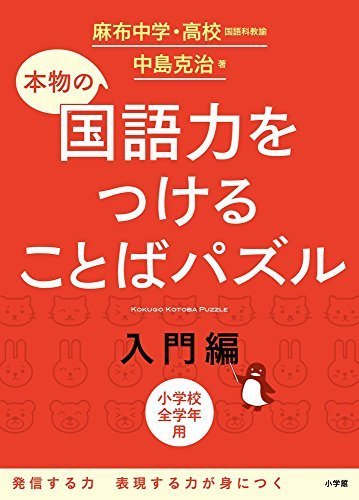中島克治氏プロフィール

1962年生まれ。麻布中学・高校を経て、東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程に進んだ後、麻布中学・高校国語科教諭となる。
著書に『できる子は本をこう読んでいる 小学生のための読解力をつける魔法の本棚』『中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚』『小学校入学前にことばの力をつける魔法の本棚』(小学館)、『20歳からの<現代文>入門 ノートをつけながら深く読む』(NHK新書)などがある。一女の父。
「本物の国語力」とは?
ーー先生が考える「本物の国語力」とはどんな力でしょうか?
中島 ひと言で言うと、「言葉になっていないものを感じ取る力」のことですね。
人は、話すときの癖などは、意外と分かっていないものです。視線、口調や体の動きなどですね。
言葉にすることには、みな緊張と責任をもつものなんですが、選んだ言葉が正しいかどうか、内面を見せることに不安を持つ人もいるわけです。
そういう相手が本当に何を言いたいのか、共感して想像する力です。
ーー相手の言葉の裏を読むということですか?
中島 そうではなく、言葉のプラスアルファをくむのです。
子どもの世界に例えると、お友達が泣いているのを見て、悲しくて泣いているのか、悔しくて泣いているのか、それともお腹が痛いのか、考えますよね。相手の気持ちを考えて共感する。これが最も大事なことです。
言葉が通じない外国の人とでも、心を通じ合わせることはできますよね。逆に、共感する力がなくては、いくら言葉を尽くしても、心にひびくことはありません。
ーーそれが、国語の力に通じるのでしょうか。
中島 そうです。読解問題では、筆者が言いたいことを文章の具体的な言葉のつながりから見つける、これが平面図になりますが、これだけでは読み取れない場合もあります。
筆者や登場人物の考え、意志、主張は何かを組み立てて、立体図にしていく作業が必要です。
例をあげると「線を引いた箇所の主人公の気持ちを答えなさい」という問題で、その人物の会話だけでなく、仕草、動き、背景まで注意してほしいということです。
子どもを育てる上で最も大切なこととは?

ーー子どもの言葉を育て伸ばすには、やはり家庭での関わりが大きいのではと思います。どのようなことに気をつければいいでしょうか?
中島 「差別しないこと」「自分を正当化しないこと」が大事だと思います。
大人は他人を選別したり、偏見を持ったりしまいがちですよね。あの人はこういうところがあるとか…。
そこまで、自分が正しいのか、他の人の意見は間違っているのか考える余裕がないのですね。
弱い人ほど、自分は絶対に間違えない、正しいと思い込んでいる傾向がありますよね。
つい大人は自分の意見を子どもに押しつけがちですが、子どもにも意志や考えがあるわけで、あなたはどう思うの?あなただったらどうするかしら?と、時々でも聞いてあげたらいいと思います。
あとは、相手の意見を否定しないことが大切です。
否定されると、子どもは思考を停止します。自由に考えをめぐらせることができなくなります。
ーー子ども相手だと、つい上から目線になり、口うるさくなってしまいます。
中島 決して難しいことではありません。
美味しいものを食べて、美味しいねと言う。ころんで擦り傷をつくってしまった子どもに、痛いねと言う。状況を共有して共感することです。
そうすれば、子どもも自然に、他者に心を寄せることを学びますし、自分の考えを話すことに対して意義を持つようになります。
自分が歩み寄るだけでなくて、相手から歩み寄ってもらうにはどうしたらいいか、考えるようになります。
それからぜひ父親も育児に関わってほしいですね。
男だから、女だからこうしなければという固定観念を取っ払って、自分を小さな枠組みの中に入れないでほしいと思います。
子どもの思考力を伸ばすには
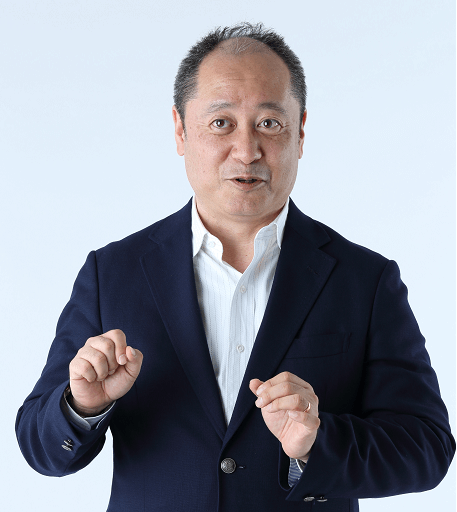
ーー2020年の大学入試改革では、思考力・表現力を重視し、「真の学力」を評価する選抜方式が検討されています。これについて、先生はどうお考えでしょうか?
中島 入試の方法にあまりとらわれない方がいいというのが私の考えです。どんな入試法になろうとも、人間として成長を阻害するものではないですから。
親御さんに申し上げたいのは、人間性は点数化されないところに伸びしろがあるということです。
テストではどうしても早さ、正確さを望まれます。ですが、ゆっくり、丁寧であることもすばらしい長所なのです。そこを親として大切にしてあげてほしいと思います。
このサイトをご覧になっている方のお子さんは、まだ小さくてテストなどはまだ先のことでしょうが、小学校にあがると直面することです。
短期間に結果が求められるときこそ、子どもの良いところを見るようにしていただきたいと思います。
ーーでも、つい、他のお子さんと比べたり、できないところが気になったりしてしまいます。
中島 親も、子どもと一緒にやってみるといいですよ。意外とできませんから(笑)。
自分も計算ミスしたり、間違えたりしますよ。
私も、娘と一緒にやっていて、娘の方がよくできるなんてことはよくありますから。
子どもも結構難しいことをやっているんだなと分かります。
どうしてできないの!と言ってしまいがちなんですが、上から目線にならないよう注意してください。
『本物の国語力をつけることばパズル』に込めたメッセージ

ーー最後に、このドリルに込めた思い、読者へのメッセージをお願いします。
中島 ドリルとしては難しくないところもありますが、様々な方向性から考え抜いたドリルになったと思います。
・品詞にこだわったこと
・インタビューなど、自分でアクションを起こすこと
・場面を想定して思考すること
など、多角的に言葉を生み出すように構成しています。
「入門編」は入学前後のお子さんを想定して作っています。
お子さんによって、ことばへの興味はそれぞれですから、あえて学年別にしていませんが、やりたいお子さんはどんどん進めてほしいです。
楽しんで取り組んでいただけると嬉しいですね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。