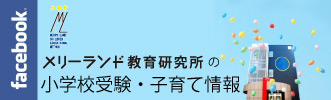メリーランド教育研究所による解説と、取り組み方のアドバイスをお届けします。
今回は「系列」に関する問題です。この問題は、順序よく並んでいるものを見て、「どのような約束のもとに並んでいるのか」を捉える問題です。法則を自分で見つける思考力、見つけた約束を生かして空欄に入る形を考える推理力が必要になってきます。これを繰り返すうちに、子供達の論理的思考力を養うことができます。
それでは、問題を見てみましょう!


Image by メリーランド教育研究所
子供への発問はこちら。
「順序良く形がならんでいます。空いている□に入る形を考えて、その形を書き入れましょう」
※小学校受験では、幼児は文章を読めない前提で行われるため、ほとんどの発問が口頭で行われます。この通りに読み上げて発問しましょう。
きちんと答えられましたか?
正解はこちらです。

Image by メリーランド教育研究所
この問題に対する解き方として、2つの例を挙げます。
【例1】
左右の手を使う方法。
同じ形どうしに指を置いて、一つずつ横に進めていきます。「片手が空欄を指したとき、もう片方の手が指している形が空欄に入るものになる」という考え方です。
図では左から右に進んでいますが、もちろん右から左に進んでも構いません。
【例2】
約束事のまとまりをとらえる方法。
この問題では、「○△×」の繰り返しだと気づくことができれば、指を使わなくても答えを出すことができます。
このように、考え方は1つではありません。お子様が解きやすい方法を見つけてあげましょう。
しかし、機械的に「同じ形に指を置いて動かす」というような教え方では思考力は身につきませんし、高度な問題に対応できなくなることも。その辺りを踏まえて次の問題にいってみましょう。

Image by メリーランド教育研究所
子供への発問は先ほどと同じです。
「順序良く形がならんでいます。空いている□に入る形を考えて、その形を書き入れましょう」
いかがでしたか?
正解はこちらです。

Image by メリーランド教育研究所
今回のポイントは、「同じ形が連続で並んでいる」ということです。
前述の【例1】の解き方をしようと、見えている2つの△に指を置いてしまうと、正解に辿り着けません。ここで、「あれ? おかしいぞ?」と気づくことが重要です。気づくことができれば、「今度は□に指を置いて、右から左に進んでみよう」というふうに考え直すことができますね。
前述の【例2】の解き方、まとまりを見つけ出す方法ならば、「今回は△△○□の4個で1セット」ということに気づく必要があります。
教えられたまま機械的に解くと間違えてしまう問題でした。お子様が考え方を理解していないと、このような小さな変化に対応できなくなってしまいます。ただテクニックを教えるのではなく、考え方を身に付けられるようにしましょう。
「系列」の問題では、決まりや規則性を発見しなければなりません。そのためには、「全体を眺めて部分の構成を推理し、思考する能力」が必要。特に難しい問題を解く際には、「粘り強く考える力」が必要になります。実は、粘り強い思考力こそ、日常の生活の中で見につくものなのです。子ども考えさせる、決めさせることを心がけ、その後の行動を褒めてあげれば、自信を持って思考する力が養われます。ペーパー上の問題を解くための力は、意外にも、日常の暮らしの中で養われるものなのです。

今回は「系列」に関する問題です。この問題は、順序よく並んでいるものを見て、「どのような約束のもとに並んでいるのか」を捉える問題です。法則を自分で見つける思考力、見つけた約束を生かして空欄に入る形を考える推理力が必要になってきます。これを繰り返すうちに、子供達の論理的思考力を養うことができます。
それでは、問題を見てみましょう!

問題
やってみよう!

Image by メリーランド教育研究所
子供への発問はこちら。
「順序良く形がならんでいます。空いている□に入る形を考えて、その形を書き入れましょう」
※小学校受験では、幼児は文章を読めない前提で行われるため、ほとんどの発問が口頭で行われます。この通りに読み上げて発問しましょう。
問題1の正解
きちんと答えられましたか?
正解はこちらです。

Image by メリーランド教育研究所
この問題に対する解き方として、2つの例を挙げます。
【例1】
左右の手を使う方法。
同じ形どうしに指を置いて、一つずつ横に進めていきます。「片手が空欄を指したとき、もう片方の手が指している形が空欄に入るものになる」という考え方です。
図では左から右に進んでいますが、もちろん右から左に進んでも構いません。
【例2】
約束事のまとまりをとらえる方法。
この問題では、「○△×」の繰り返しだと気づくことができれば、指を使わなくても答えを出すことができます。
このように、考え方は1つではありません。お子様が解きやすい方法を見つけてあげましょう。
しかし、機械的に「同じ形に指を置いて動かす」というような教え方では思考力は身につきませんし、高度な問題に対応できなくなることも。その辺りを踏まえて次の問題にいってみましょう。
問題2
難易度が上がります。

Image by メリーランド教育研究所
子供への発問は先ほどと同じです。
「順序良く形がならんでいます。空いている□に入る形を考えて、その形を書き入れましょう」
問題2の正解はこちら。
いかがでしたか?
正解はこちらです。

Image by メリーランド教育研究所
今回のポイントは、「同じ形が連続で並んでいる」ということです。
前述の【例1】の解き方をしようと、見えている2つの△に指を置いてしまうと、正解に辿り着けません。ここで、「あれ? おかしいぞ?」と気づくことが重要です。気づくことができれば、「今度は□に指を置いて、右から左に進んでみよう」というふうに考え直すことができますね。
前述の【例2】の解き方、まとまりを見つけ出す方法ならば、「今回は△△○□の4個で1セット」ということに気づく必要があります。
教えられたまま機械的に解くと間違えてしまう問題でした。お子様が考え方を理解していないと、このような小さな変化に対応できなくなってしまいます。ただテクニックを教えるのではなく、考え方を身に付けられるようにしましょう。
まとめ
「系列」の問題では、決まりや規則性を発見しなければなりません。そのためには、「全体を眺めて部分の構成を推理し、思考する能力」が必要。特に難しい問題を解く際には、「粘り強く考える力」が必要になります。実は、粘り強い思考力こそ、日常の生活の中で見につくものなのです。子ども考えさせる、決めさせることを心がけ、その後の行動を褒めてあげれば、自信を持って思考する力が養われます。ペーパー上の問題を解くための力は、意外にも、日常の暮らしの中で養われるものなのです。
・掲載内容や連絡先等は、現在と異なる場合があります。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。