【映画化された児童書(1)】「雪の女王」
「アナと雪の女王」にインスピレーションを与えたアンデルセンの名作メルヘン
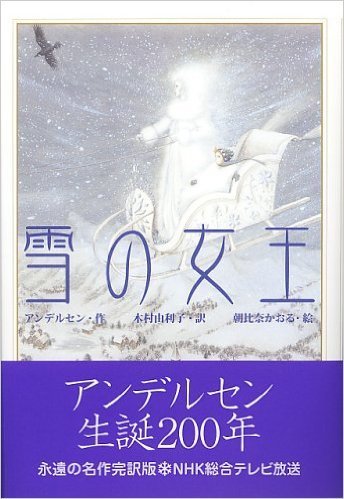 出典:amzn.to
出典:amzn.to最初のおすすめはデンマークの童話作家アンデルセン作「雪の女王」です。旧ソ連、イギリスなど多くの国で映像化されてきましたが、日本でも2005年にNHKでアニメ化されています。
こちらはあの大ヒットディズニーアニメ「アナと雪の女王」の原案となったことでも有名です。
ディズニー版はまったく新しいストーリーを創りだしていますが、話のプロットや小道具にちょこちょこと面影があるのが面白いところです。
本家「雪の女王」も幼なじみの少年カイと少女ゲルダというダブル主人公です。
悪魔が作った鏡の欠片が目と心臓にささって、冷たい性格になってしまったカイは、雪の女王にさらわれてしまいます。
カイのことを忘れられないゲルダは、カイを探しに冒険と驚きにみちた旅にでかけますが…。
さまざまな花や動物に道をたずね、ときに追いはぎに襲われたりという苦難にもめげずに最後には大好きなカイを探しだしてある方法で鏡の欠片を取り除きます。
最初から最後まで、選びぬかれた言葉とイメージングによる最上のメルヒェン(童話)を味わうことができるこの作品。
描きだされる世界のうつくしさに、ため息がでてしまいます。アンデルセンの最高傑作との声にも納得です。
またこれは、少女ゲルダが少年カイにささげる純愛の物語でもあります。どんな苦境におちいっても決してあきらめず、ひたすらにカイを探し求める強い姿はうつくしい!
女の子って、どんなに小さくってもだれかに惚れちゃう生き物なんだなと思わせられます。この強さ、「アナ雪」のアナにもなぞらえられるところです。
反面、本家「雪の女王」に登場する冷酷な雪の女王は「アナ雪」のエルサの役どころとなりますが、ディズニー版は雪の女王の冷酷を苦悩に置きかえ、二人の女性の成長と変革(エルサ=自己の解放、アナ=子どもから大人の女性への成長)をストーリーの幹としたところが、大きな成功につながったのではないでしょうか。
古今東西、刺激的なインスピレーションを与え続ける「雪の女王」。
寒くなってきましたので、温かいお茶でも飲みながら一読してみては? ちなみにトナカイもでてきますよ!
今回、ご紹介した商品の詳細はこちら
【映画化された児童書(2)】「星の王子さま」
誰もが持つ「こころの中の子ども」に訴えかける永遠のピュア・ストーリー
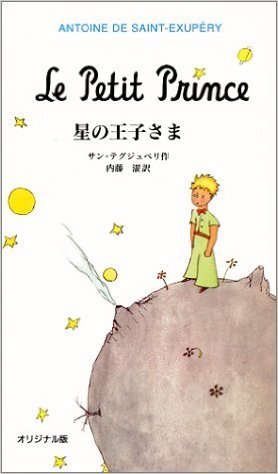 出典:amzn.to
出典:amzn.to次に、2015年に「リトルプリンス」として映画化されたサン=テグジュペリ原作「星の王子さま」をご紹介します(ちなみに筆者はマーク・オズボーン監督と聞いて一瞬エッとなってしまいました。「カンフーパンダ」のイメージがあったので 笑)。
これはもう、まだお読みになってない方には「早く読んで、今すぐ読んで、さあ読んで!」としか申し上げられないくらいの古典的名作です。
ちなみに筆者は小学生のころにこの本に出会い、いまでは箱根の「星の王子さまミュージアム」にも行ってきたくらいのファンです。
でもね、最初に読んだころには「つまらない本だな」と思いましたよ。
ストーリーといえば、サハラ砂漠に不時着した飛行士が、水さえ満足にない孤独のなかで、星からきたというひとりの不思議な少年に出会って、延々その話を聞くというだけのシンプルなお話です。
主人公は、王子さまの星に咲いていたバラの話をはじめとして、地球にくるまでの星々の旅で出会った人々の話や、地球にきてから出会ったヘビやキツネの話をします。
主人公は飛行機をけんめいに修理するかたわら、王子さまの話にじっと耳をかたむけます。
王子さまが星に帰っていく最後のくだりは、悲しいですが、同時に喜びと安らぎにみちたものです。
1行1行に寓意がこめられた哲学的ともいえる作品だけに、「星の王子さま」の書評は山とあって、解釈や受け取り方は本当に千差万別です。
そこにひとつ付け加えるとするなら、筆者はこの本に「しっかりと話を聞くことの大事さ」を教えてもらったような気がします。
だって、主人公の「ぼく」がおかしなフィルターをかけることなく、無心に王子さまの話に耳をかたむけなければ、どんなすばらしい言葉も聞くことはなかったわけですから。
「星の王子さま」、映画といっしょに原作をぜひ一読して自分なりの解釈を見つけてみてくださいね。
今回、ご紹介した商品の詳細はこちら
【映画化された児童書(3)】「ピーターパン」
大人になることを捨てた「子ども」の残酷さをも描きだす名著
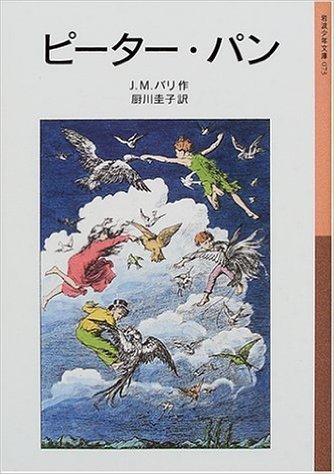 出典:amzn.to
出典:amzn.to最後にイギリス人作家ジェームズ・バリによる、ご存じ「ピーター・パン」をご紹介します。
最初に注意すべきは、この「ピーター・パン」には主に2つのバージョンがあるということです。
ディズニー映画で有名な「ピーター・パン」(ティンカーベルやフック船長がでてくる)は、じつは1911年に書かれた「ピーター・パンとウェンディ」を土台にしています。
これ以前の1906年にも、その原点となる「ケンジントン公園のピーター・パン」という短編が発表されています。
しかしこちらはピーター・パン以外はまったく登場人物が違い、ピーターパンの年齢も、作品の主旨も異なりますので別物といってよいでしょう。
「ケンジントン公園~」の主人公ピーター・パンはずーっと生まれて1週間の赤ん坊(!)で、ネバーランドにも行きませんのでご注意を。
順番としては、原型である「ケンジントン公園のピーター・パン」から読むのがいいかもしれません。
「ケンジントン公園~」の世界では、人間は最初みんな鳥としてこの世に生まれてくるんですね。
それから人間としていわば転生するわけですが、ピーター・パンは生後1週間で鳥の世界が恋しくなって、窓から飛んでいってしまいます。
でもその後飛ぶことができなくなって、お母さんのところに帰れなくなってしまい、鳥でも人間でもない「どっちつかず」として永遠の時を生きていく…というもの。
とっても切ないですが、異界の描写がうつくしく、神話的な性格を持ったお話です。
また、「ピーター・パンとウェンディ」ではピーター・パンの仲間たちとフック船長らがネバーランドで冒険劇を繰り広げるわけですが、ディズニー版「ピーター・パン」とはいささかキャラクターの描写が異なります。
原作のピーター・パンは正義とは無縁の存在です。そこで描かれるのはひたすら子どもの奔放さと無邪気。
身勝手さ、と言いかえることもできます。殺すことをためらいませんし、成長した子どもをグループから間引いたりもします。残酷ではありますが、幼児性の本質をするどく描きだしているともいえます。
旅の終わりには、ピーター・パンは家に帰るウェンディに置き去りにされてしまいます。
そして次はウェンディの子どもをさらい、そしてまた「置き去りにされ」、次はまたその子を…。
「ケンジントン公園」バージョンとも共通しているのは、ピーター・パンが永遠に置き去りにされる孤独な存在であるということ。
子どもであることの残酷さ、そして子どもであり続けなくてはならないことの残酷さ。
「ピーター・パン症候群」なんて言葉もありますが、ずっと子どもでいるということは、それだけ人間にとって異質であり危険がともなうことを暗示しているのかもしれません。
今回、ご紹介した商品の詳細はこちら
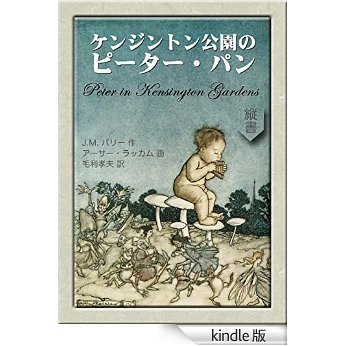 出典:amzn.to
出典:amzn.toちなみに1991年に発表されたスピルバーグ監督の「フック」は、上記の2バージョンを上手に組みあわせた内容になっていますね。
ジェームズ・バリ作「ピーター・パン」2バージョン、この機会にぜひ読み合わせてみては?
大人とは何か、成長とは何かを考えさせてくれますよ。
今回、ご紹介した商品の詳細はこちら
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回の記事では映画化された児童書を取りあげましたが、どれも子どもたちに「子ども時代にこそ出会ってもらいたい」本ばかりです。
また、良質の児童書は含蓄やメタファーに飛んでいて、大人が読んでもじゅうぶんに面白いものです。
自分の年齢と共に、読み方が変わってゆくものでもあります。映画と原作とのギャップを含め、ぜひいろんな観点から読書を楽しんでくださいね♪
この記事に関連するリンクはこちら
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。






